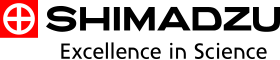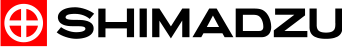基本的な考え方
当社グループは、経営の透明性・公正性を確保し、経営の活力を高める迅速・果敢な意思決定と施策を遂行するための企業経営の根幹となる仕組みとしてコーポレート・ガバナンスを位置付け、このシステムを整備・充実させています。
当社は、コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)を具体的に実践していく上でのスタンスを示すものとして、「コーポレートガバナンス・ポリシー」(以下、CGポリシー)を2015年12月に定めました。
当社はコーポレート・ガバナンスの取り組みを充実させるとともに、取り組みの状況や外部環境の変化に応じてCGポリシーを定期的に見直し、ガバナンスの実効性の向上に努めています。
コーポレートガバナンス・ポリシー
- ステークホルダーとの適切な協働
- 株主の権利・平等性の確保
- 適切な情報開示と透明性の確保
- 株主との対話
- 取締役会などの責務
コーポレート・ガバナンスの取り組み
CGコードに関しては、プライム市場のみに適用される項目を含め、すべての基本原則、原則および補充原則についてフルコンプライを継続しています。
2024年度における当社のコーポレート・ガバナンスに関する主な取り組みは、以下のとおりです。
サステナビリティ経営の取り組みを推進
「島津グループサステナビリティ憲章」および「島津グループサステナビリティ経営実施方針」のもと、各部門のKPIを設定し、当社グループのサステナビリティ経営に関する取り組みを本格的に開始しています。
その一環として、当社グループ全体で法令遵守の徹底および企業倫理の向上により一層取り組むため、2022年5月に従来の企業倫理規定を改訂し、「島津グループ企業倫理規定」として、当社グループ共通規定としました。また、当社グループの従業員が日常の業務の中で遵守すべき行動規範を「島津グループ企業倫理行動規範ハンドブック」としてまとめ、グループ全体への企業倫理・コンプライアンス意識の浸透を図っています。
さらに、2022年6月に「島津グループサステナビリティ経営基本規定」を制定し、サステナビリティ経営に関する取り組み推進の枠組み、組織体制を明確化しました。
これにより、「島津グループサステナビリティ会議」をサステナビリティ経営の最高審議機関として位置付け、従来のリスク倫理会議、環境会議を含めた当社グループ全体のサステナビリティ経営に関する取り組みを推進しています。
サステナビリティ経営の取り組みを機関投資家向けにより分かりやすくお伝えするため、2024年10月に初めて、島津グループサステナビリティ経営説明会を開催しました。今後も同様の機会を設けることで、取り組みの推進と情報発信に努めます。
サステナビリティ
https://www.shimadzu.co.jp/sustainability/index.html
グループガバナンスの強化
2023年2月に「島津グループマネジメント基本規定」を制定し、グループマネジメントに関する基本的な考え方および遵守すべき事項を定めました。これにより、当社グループが一体となって持続的成長に向けて適正かつ効率的なグループ経営を実現するための体制を整備しています。
また、海外地域コーポレート本部では、中国とアジアの現地体制が主体となって、本社が策定した監査ツールを活用し、往査計画を立てて取り組んでいます。島津グループマネジメント基本規定に則り、各グループ会社でのルール運用を確認し、不適切な手続き等の防止につなげています。
コンプライアンス・リスクマネジメント
https://www.shimadzu.co.jp/ir/governance/group.html