ヨーロッパの著名なオーケストラで客演を続け、世界から賞賛される日本人指揮者。
佐渡裕さんは、あふれる笑顔とエネルギーでオーケストラを率い、若手音楽家の育成にも力を入れる。
少年時代の憧れ、音楽への尽きぬ愛、そしてこれからの夢を語っていただいた。
バーンスタインに導かれて
幼い頃から、私のそばには音楽がありました。
母は若い頃プロのオペラ歌手で、結婚後は自宅でピアノや歌を教えていました。父親は数学教師で、自分にも他人にも厳しい人。そんな両親のもと、幼少の頃から音楽の素晴らしさと厳しさを自然と感じ取っていました。
ピアノは何歳から触っていたのかわからないくらいだったこともあり、小学校でも音楽は得意でした。当時子どもたちに人気だったアニメの主題歌は、聴くだけでリコーダーで再現できたので、クラスの友達がそれに合わせていつの間にか大合唱になることも。そのときの楽しさが指揮者の原体験です。
指揮者を目指したきっかけは、1枚のレコードでした。当時家に大きなステレオがあり、兄の教育用にとカラヤンのレコードばかり数十枚置いてあったのですが、まだ小さい私には勝手にレコードに針を落とすことを許してもらえませんでした。
それが、小学校5年のときに「自分の小遣いで買ったレコードなら針を落としていい」ということになり、最初に選んだのがレナード・バーンスタインの作品。彼がニューヨーク・フィルを指揮した、マーラーの交響曲第1番です。
当時の有名な指揮者と言えばバーンスタインとカラヤン。先に針を落とすことを許されていた兄がカラヤンなら僕はバーンスタインだ!と。普通の小学生なら歌謡曲とか選びそうですが、珍しい兄弟ですよね。
私はそのレコードを繰り返し聴き、箸を持って、コタツの上で指揮のマネをするようになりました。たわいもない遊びですが、本人は真剣そのもの。小学校の卒業文集には「将来はベルリン・フィルハーモニーの指揮者になる」と書きました。
のちに知ったことですが、バーンスタイン初来日は1961年の春。私が生まれた年です。また、友人が私だと勘違いして持ってきた当時の新聞には、今の私の指揮ポーズそのままのバーンスタインがいました。その新聞は1961年5月14日付だったのですが、その前日13日がまさに私の誕生日。
さらに、子どもの時から大好きだった小澤征爾さんがカラヤンの弟子であり、バーンスタインの副指揮者であることもわかり、自分のなかで運命的なつながりを感じずにはいられませんでした。
高校は、京都市立堀川高校の音楽課程に進みました。学園祭では学年全体で手作りのオペラを一から作るのですが、ジャンルを超えて一つのことをみんなで作っていき、タクトを振ったのはよい経験でした。
高校でも専攻していたフルートを京都市立芸術大学でも専攻しましたが、在学中から中学、高校のブラスバンドや、ママさんコーラスの指揮などを請け負い、指揮者としてお金をいただくようになりました。一日3000円のギャラが5000円に、いつしか1万円になり、「これでメシを食っていけるかもしれない」と漠然と思い始めたのもこの頃でした。
ただ、指揮者というのは、どうすれば就けるのかわからない職業なんです。どうしたものかと思案しているときに、友人が「タングルウッド音楽祭」に聴講生として参加したことを知りました。タングルウッド音楽祭は、世界の一流アーティストが集う最高峰の音楽祭。若い音楽家が学ぶ場所でもありました。彼はそこでバーンスタインや小澤さんのサインをもらったそうで、そのサイン帳を見せてもらったときに、「絶対自分もここに行くんだ」と決意しました。
指揮を学びたいと調べ、どうせなら一般受講生ではなく特待生を目指すことにしました。出せという指示はなかったのですが、当時珍しかった8ミリビデオで撮ったリハーサル映像を添えて申し込みをしたところ合格。幸運なことに私は、小澤さんと出会い、バーンスタインに師事することを許されたのです。人生が180度変わった瞬間でした。
その後、たった3年間でしたが、音楽の捉え方、譜面の読み込み方、演奏者との接し方など、バーンスタインから教わったことは、数限りなくあります。指揮棒でコントロールするのではなく、奏者が自発的に表現できるようにするにはどうしたらよいかを考えるようになりました。
一番大きいのは、「指揮者とはこうあるべき」という枠から解放してもらえたことでしょうか。タクトの振り方にしてもそう。型通りである必要はない。ときにはオーケストラを鼓舞し、勇気を与えるのが指揮者。そのためには拳骨を突き上げることがあってもいいのです。
バーンスタインは才能の塊のような人でした。音楽にはとても厳しい一方で、普段は本当に気さくで自然体。ジョークやいたずらも大好きで、まるで親友のように接してくれました。ツアーにも同行させてもらい、高級リムジンやプライベートジェットでの移動など、世界のスーパースターとはこういうものだという非日常を味わったことも、得難い体験でした。

次の世代につなげる
あるとき私はバーンスタインに、「これまでの人生で、一番印象に残っている仕事は?」と質問しました。ニューヨーク・フィルのマーラー全集、ウィーン・フィルと演奏したベートーベン、スカラ座でマリア・カラスとつくり上げたオペラなど、数々の名演で知られていますが、答えは「子どもたちのための演奏会」というものでした。本来であれば、指揮者のデビューに使われるような場です。当時は彼の冗談だと思っていました。
バーンスタインは1958年から1972年にかけてテレビ番組「ヤング・ピープルズ・コンサート」を制作しています。子どもにクラシック音楽を紹介する番組なのですが、それを後で取り寄せて見たところ、この内容が本当に秀逸で、音楽の素晴らしさ、オーケストラの魅力が多くの人に伝わるものでした。次の世代を育てることがもっとも大事な仕事だと考えるバーンスタインらしさでもあり、私への教えでもありました。いまでも私の原点です。
30代までは自分の仕事で精一杯でしたが、40代に差し掛かる直前、転機が訪れました。1999年から始めた「佐渡裕 ヤング・ピープルズ・コンサート」です。
バーンスタインが1990年に亡くなったあと、彼の家族から「裕は自分の“ヤング・ピープルズ・コンサート”をつくるべき」と言っていただけたことで、バーンスタイン亡き後も彼の意志を引き継ぎ、後世につなげる活動を始めることができました。
のちに『題名のない音楽会』の司会もやりましたが、多くの人に音楽の素晴らしさを伝え、次の世代につなげる仕事はとてもやりがいがあります。
2005年に開館した兵庫県立芸術文化センターの芸術監督にも就任しました。この劇場を中心に活動しているスーパーキッズ・オーケストラ(SKO)、兵庫芸術文化センター管弦楽団(PAC)もまた、若い世代の育成、サポートを目的としています。

厳しいオーディションで選ばれた子どもたちによるSKOは、世界がアッと驚くようなオーケストラをつくりたいという目標を掲げています。こんなことを言うと他のオーケストラのメンバーがやきもちを焼くかもしれませんが(笑)、もっとも愛情を注ぎ、スケジュールも最優先しています。最初の卒業生がデンマーク王立管弦楽団のヴィオラ奏者になるなど、素晴らしい成果も生まれています。
何よりも嬉しいのが、彼ら、彼女らと音楽を演奏することを通し、家族以上とも言える関係になれること。もっとも多感な時期を一緒に過ごし、共に音楽をつくっていくことが、みんなにとってかけがえのない経験になれば、これ以上の喜びはありません。
子どもたちはとても真剣に、私がどんな音楽を求めているかを考え、実践します。実際、SKOが奏でる音は、佐渡裕がつくりたい音そのもの。自分の姿を映し出す鏡のようです。夢を描けているか、やる気を持っているか、私自身の変化も彼らの音にはっきり表れる。
それがおもしろくもあり、責任も感じています。だからこそ愛情を持って接する。彼らが夢を持ち情熱を燃やして邁進し続けるためにも、全身全霊で向き合っていく指導者でありたいですね。
PACは日本、アメリカ、アジア、ヨーロッパなどから集まった若手プロの集まり。年間100本以上の公演をこなしながらも、世界で活躍する演奏家を目指し、アグレッシブに経験を積んでいくと同時に、世界中のオーケストラのオーディションを受けるためのサポートをしたり、アカデミーとしての役割も果たしています。
心の広場になる
コロナ禍のもと、世界中の音楽家が大きなダメージを負っています。オーケストラは本来、互いに近いところで音を聴き合いながら演奏しなければなりません。コロナ禍以降は、専門家の医師とも協力しながら、どうすれば安全に演奏できるか模索を続けています。もちろんコンサートのときも、ガイドラインを守り、さらに独自の工夫をしながら、観客のみなさんに安心して鑑賞していただける環境を整えています。
昨年の春には初めて動画の配信も行いました。我々のスローガンは、“心の広場”になること。コンサートができない、先が見えない状況だからこそ、多くのみなさんに楽しんでもらえる音楽を発信するべきだと考え、PACのメンバーとともに「すみれの花咲く頃プロジェクト」を立ち上げました。
まず、私が一人で舞台に上がり、指揮をしている映像を撮る。さらにオーケストラのメンバーや、楽器や歌を習っている一般の方々に演奏していただき、それを合わせて一つの映像に。32のバージョンをつくり、約400名の方々に参加していただけたことは、大変感慨深いですね。
オンライン配信には確かな手ごたえがありましたが、同時に「早く劇場で演奏を聴きたい」というみなさんの強い思いも感じました。私自身改めて生の演奏の大切さを感じました。
全く知らない人たちと一つの空間を共にしている素晴らしさ、空気が振動している体感、拍手の熱量。耳で聴くだけではない音楽は、心にビタミンを届けるものであり、生きていくために必要なもの。「みんなと会って、共に音楽を奏でたい」という気持ちがさらに強くなりました。
この7月には夏のオペラを2年ぶりに再開し、「メリー・ウィドウ」を上演。楽しい物語と、耳馴染みのよいメロディーが愛され、世界中で数多く上演されていますが、今回の公演は、関西ならではの演出を加えています。
ひとつは、宝塚歌劇団のテイスト。“銀橋”を使った舞台や、20分に及ぶグランドフィナーレなど、関西の舞台芸術の基礎をつくった宝塚のエッセンスを取り入れたのです。
もうひとつはお笑い。狂言回しの役で桂文枝さんに出演していただき、上方のお笑いの要素も存分に発揮していただきました。
「指揮者の旬は60歳から」と言われます。私も還暦を迎え、自分の経験値が積み上がってきたことを感じています。ただ同時に「まだまだ素人」という思いもありますね。これまでは兵庫、東京、ヨーロッパを中心に活動してきましたが、近い将来、アメリカで活動するのもいいなと思っています。
ヨーロッパにも、まだ振ったことがない名門オーケストラがありますし、実現したいことはまだまだある。じつは定年退職にも憧れているのですが(笑)、数年先のスケジュールも決まっているし、当分引退するわけにはいかないようです。
※所属・役職は取材当時のものです

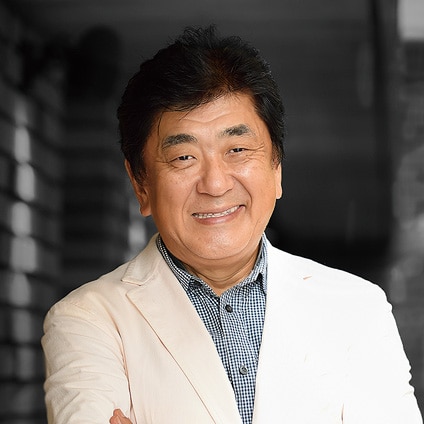
- 佐渡 裕(さど ゆたか)
-
1961年、京都府出身。故レナード・バーンスタイン、小澤征爾に師事。1989年ブザンソン国際指揮者コンクール優勝。以後毎年ヨーロッパの一流オーケストラへ多数客演を重ね、世界的な活躍を続けている。2015年よりオーストリア、ウィーンの名門で110年以上の歴史を持つトーンキュンストラー管弦楽団音楽監督に就任。国内では兵庫県立芸術文化センター芸術監督、シエナ・ウインド・オーケストラ首席指揮者を務める他、2023年4月より新日本フィルハーモニー交響楽団音楽監督に就任予定。
記事検索キーワード
VOL.45その他の記事
-
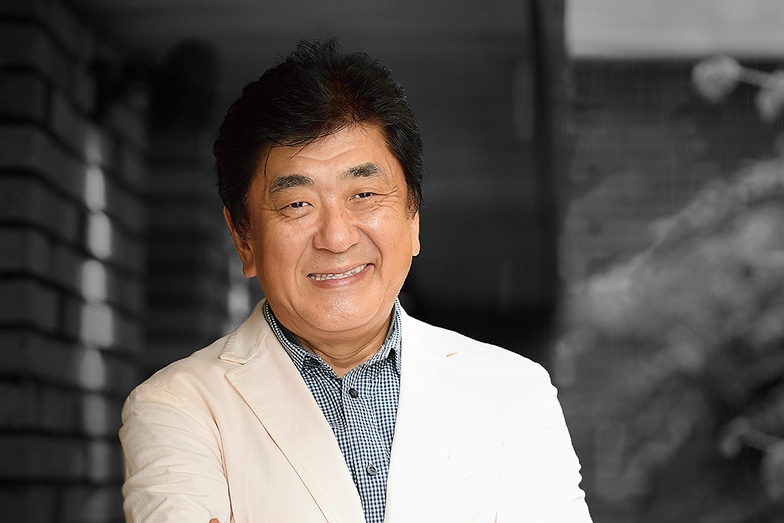 特集音楽に導かれ、そしてタクトで次の世代につなぐ 佐渡裕さんインタビュー
特集音楽に導かれ、そしてタクトで次の世代につなぐ 佐渡裕さんインタビュー -
 VOL.45みんなでつくるバリアフリーマップで、車いすでもあきらめない世界を
VOL.45みんなでつくるバリアフリーマップで、車いすでもあきらめない世界を -
 VOL.45しょうゆを世界の食事風景の一コマに
VOL.45しょうゆを世界の食事風景の一コマに
キッコーマンが研究する「おいしい記憶」 -
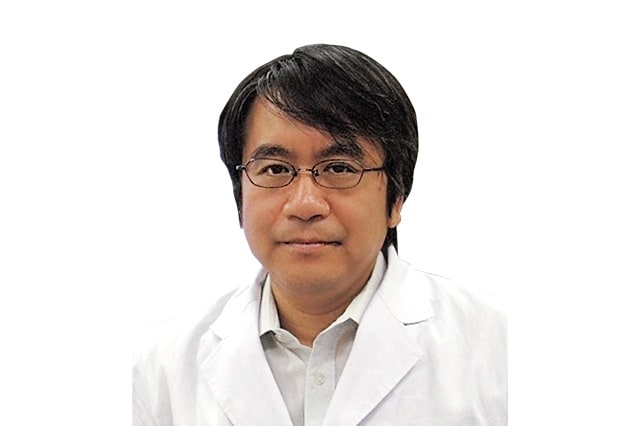 VOL.45アルツハイマー病のリスクを発見する血液バイオマーカー研究のトリガーを引いた研究者らの熱意
VOL.45アルツハイマー病のリスクを発見する血液バイオマーカー研究のトリガーを引いた研究者らの熱意 -
 VOL.45自動車産業100年に一度の大変革期
VOL.45自動車産業100年に一度の大変革期
安全なモビリティであり続けるために島津が担う役割 -
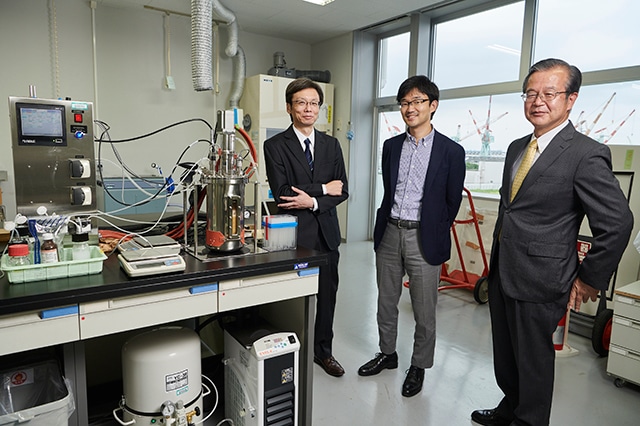 VOL.45微生物の力でつくる“バイオ”タイヤ
VOL.45微生物の力でつくる“バイオ”タイヤ
石油に頼らない未来を目指して -
 VOL.45平等ではなく公正に
VOL.45平等ではなく公正に
“フェア”マネジメントがチームを変える -
 VOL.45医療現場のためのより簡便な検査装置を 日本の課題に挑んだクリニック向け全自動PCR検査装置開発の道のり
VOL.45医療現場のためのより簡便な検査装置を 日本の課題に挑んだクリニック向け全自動PCR検査装置開発の道のり -
- NEWS & TOPICS2021年2月~2021年8月
-
- 2021.3.17/4.1/5.6/7.15PCR検査で変異株の検出を迅速化し、疫学調査の効率化に貢献
変異株のスクリーニング検査も支援 - 2021.2.25/3.26/4.8/5.13/6.2/7.12下水とヒトの2階建て
新型コロナウイルスPCR検査システム「京都モデル」の構築
PCR検査体制の整備拡大への貢献 - 2021.6.23MBL社の新型コロナウイルス不活化液の開発に協力
PCR検査の検体輸送と前処理の安全性向上に貢献
- 2021.3.17/4.1/5.6/7.15PCR検査で変異株の検出を迅速化し、疫学調査の効率化に貢献


