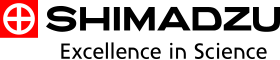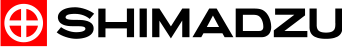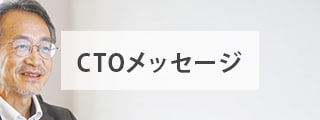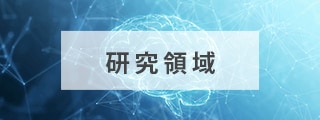プラネタリーヘルスの追求と研究開発
当社グループの中期経営計画ではテーマとして「プラネタリーヘルス」を掲げ、新製品および新事業の開発にもこれを展開して活動を進めています。
プラネタリーヘルスは、「地球の健康」と「人間の健康」が相互に関係しているという考え方と言われています。そのため、多様な社会課題を総合的に捉えることが必要で、その解決を図ることが求められています。当社グループの経営理念である“「人と地球の健康」への願いを実現する”にも密接に関係する概念であり、私たちにとってこの言葉は古くて新しい内容です。今あらためてその内容を深く理解し、プラネタリーヘルスのために私たちができること、やるべきことは何かを考え、実行する時であると感じています。
私たちの事業では技術ベースの新製品、新事業となるケースが多く、技術者、研究者にとって重責であるとともに、やりがいのある仕事でもあります。このたび、CTOに着任し、その任務を果たしていくことになりますが、技術の会社として技術者が生き生きと働き、ワクワクしながら新しい研究・開発に取り組めること、そこから新規アイデアが次々と生まれること、そのためのイノベーションマネジメントの仕事が中心にあるものと考えています。
企業の技術者として駆け出しのころから育てていただいた先輩方に、プラネタリーヘルスの事業拡大として恩返しをすることを考えると、改めて身が引き締まる思いです。技術の枠を超えてグループ全体で協力・連携し、新しい挑戦をしていきます。
中期経営計画2年目の成果
現在の中期経営計画では、研究開発部門の取り組みとして、以下の3つの戦略を遂行しています。
① グローバルでの開発力向上
② 開発プロセスの改革
③ 新技術・事業創出力の向上
顧客に密着したグローバル製品開発体制の構築とソフトウェアのグローバル分散開発体制構築に向けた取り組みを推進しました。2024年4月に開設した北米R&Dセンターは製品開発に向けた設計環境など運用への支援を行いました。ソフトウェアのグローバル開発では、各拠点でセキュリティを強化したサービス環境の構築を進めました。既に、本社では運用を開始しており、順次関係会社への展開・拡大を進めています。
開発プロセスの改革では、アジャイル開発手法の追加と設計DXの構築を進めています。アジャイル開発はまだ一部の施行にとどまっており、今後の本格展開が課題です。設計DXでは設計、製造、品質データの一元管理と蓄積、データ活用は新業務フローを実証中です。
新技術・事業創出力の向上では、新事業・将来事業に向けた開発を進めるとともに、2023年度に設立したCVC(Shimadzu Future Innovation Fund)でのスタートアップ投資を進めています。2年目となる2024年度は計画を超える7件実行しており、投資分野としてもヘルスケア1件、グリーン3件(うち2件はマテリアルにも該当)、インダストリー3件の実績と、2023年度の課題であったヘルスケア以外の分野の投資が加速しました。
課題と今後の取り組み
新製品の早期市場投入の観点から、研究開発分野でのいくつかの課題があり、今後必要な施策を進めます。研究フェーズでは、研究者の発想を広げる、またアイデアを素早く試す体制作りの課題に対して基盤技術研究所でいくつかの取り組みを試行してきました。これらの効果を検証し、有効なものは部門を広げて実行していきます。また、要素技術から製品設計に向けスムーズな技術移管のためにも必要な施策を進めます。要素技術開発を行う部門と製品化を行う部門の開発早期からの連携体制構築や開発フェーズにおける設計DXによる効率化などを推進します。これにより、開発業務専念による開発スピードアップ、品質の向上が期待できます。
また、先進技術領域に対し、シリコンバレーの駐在員を通して海外機関と連携した投資および協業も進めていきます。出向や協業を通じた研究開発人財の育成も重点的に取り組む項目の一つです。
素早く新製品を世の中に出していくために、オープンイノベーションの拡大・強化施策についても積極的に進めており、その一つとして研究パートナーの公募制度「みらい共創チャレンジ」を新たにスタートしました。これは、今後必要となる領域を設定し、提案されたテーマの中から採択されたテーマについて共同研究として実施するものです。必要に応じて当社グループが保有する機器装置等も活用いただきながら、成果に応じてさらなる大型プロジェクトへ発展する可能性もあります。今回は、超高齢化社会、産業の発展のための新材料開発などの課題に対し、多数の独創的な提案をいただくことができました。今後も年に1回程度の公募を実施していきます。
150年から始まるみらい共創
今年創業150周年を迎える当社の研究開発の歴史は、オープンイノベーションの歴史でもあります。明治期の舎密局(せいみきょく)との共創、第三高等学校とのX線装置の開発から始まり、さらに鉄鋼産業、石油化学、製薬などそれぞれの時代で日本の産業を支えてきた業界の方々からのご指導等を通し、技術を磨き、製品を世の中に送り出してきました。近年では、ヘルスケアR&Dセンターの設立、基盤技術研究所みらい共創ラボの開所、Shimadzu Tokyo Innovation Plazaの開設など共創を目的とした拠点整備が進みました。共創の結果として社会に貢献できる研究成果も見えてきつつあります。東京大学・香取教授との共同研究で進めてきた超高精度の時間計測が可能な「光格子時計」は受注開始の発表をすることができました。100億年に1秒という誤差の時計は、一般相対論の原理で重力ポテンシャルを時間の進み方の違いとして計測することができ、地殻変動の計測に使える可能性もあります。また量子計測の応用も進み、京都大学・竹内教授との共同研究を進めている量子もつれ現象を用いた赤外分光も実用化に向けた研究を急ピッチで進めています。そのほか、高性能質量分析、人の感性計測、自律型実験システムをはじめ、社会課題解決に貢献できる製品の早期上市に向けて技術者・研究者の熱い活動が続いています。この活動が150年を超え、200年に向けてさらに共創を加速し、プラネタリーヘルスに貢献する製品・事業につながるものと確信しています。今後の成果にご期待ください。
常務執行役員
CTO 西本 尚弘
略歴
| 1989年 3月 | 当社入社 | |
| 2003年10月 | 基盤技術研究所 主任研究員 | |
| 2014年 4月 | 基盤技術研究所 副所長 兼 基盤技術研究所 新事業開発室 室長 | |
| 2020年10月 | 経営戦略室 グローバル戦略ユニット ユニット長 | |
| 2022年 4月 | 基盤技術研究所 所長 | |
| 2024年 4月 | 執行役員 基盤技術研究所 所長 | |
| 2025年 4月 | 常務執行役員 CTO(現在に至る) |