“ダイバーシティ”という言葉が定着して久しいが、多くのマネージャーは多様化し続けるメンバーに配慮するのが精一杯で、その多様性を強みに結び付けられているだろうか?
一人ひとりの個性が発揮され、チームでなければ成し得ない成果に結実させるために何をするべきなのか。ダイバーシティ研究の第一人者に聞いた。
「表層」と「深層」のダイバーシティ
ビジネス環境の変化が速度を増し、一年先ですら予測がつかなくなっている現在、組織内の多様性を高めることは、変化に対応する大きな力になる。いまやダイバーシティ推進に異論を唱える声は少なく、さまざまな属性の社員が共に働く姿が日常的になりつつある。
しかし、多様な社員に配慮するだけに留まってしまい、せっかくの多様性を成果につなげられていないマネージャーも少なくない。
早稲田大学商学学術院の谷口真美教授は、こうした課題は「表層のダイバーシティに気を取られ、深層のダイバーシティに目が向いていないことが理由の一つ」と話す。
「表層のダイバーシティ」とは、性別や年齢、人種など生まれ持ったものであり、本人の意思で変えにくい属性をいう。対して「深層のダイバーシティ」は、経験や価値観、考え方などを指し、たとえ同じ表層属性であっても人によって異なる。こうした違いに向き合い、受け入れるインクルージョンの視点を持ち、組織の強みとしていかすことが「イノベーションの源泉となる」と谷口教授は強調する。
「たとえば、自分の強みではなく、女性だからという理由で採用されたと知れば、モチベーションが下がってしまいます。力を発揮してもらうには、個が持つ深層のダイバーシティに向き合う必要があるのです」
マネージャーも組織の多様性の一つ
企業のダイバーシティは、いまやどんな人的資本を保有しているかが、投資家が企業の良し悪しを判断する際の指標の一つともなっている。だが、表層は可視化しやすい一方で、その人の職歴はまだしも、価値観や物事の捉え方など、まさに人の“深層”部分は、簡単にデータベース化できるものではない。谷口教授によれば、深層は直接的な対話によって見えてくるものであり、チームでどんな役割を果たし、メンバーとの相乗効果が得られるかは現場でしかわからず、一朝一夕で引き出せるものではないという。
前提になるのは、職場の心理的安全性だ。しかし、
「深層をいかして多様な意見を交え、結果に結び付くようなポジティブなフローを働かせるには、自分の意見が成功につながり、組織に変化をもたらしているという実感が必要です。心理的安全性だけではイノベーションを起こす環境にはならないのです」
これは、部下に対してだけでなく、上司にも言えるという。
「上司自身も会社のなかに心理的安全性があり、自身やチームのもたらした変化が、組織を変えている実感につながれば、取り組みの本気度は変わります。経営陣がそうした組織風土を作ることが重要で、現場のマネージャーに『任せた』と放任するのではなく、会社としてマネージャーを支援する工夫が不可欠です」
共通のゴールや方向性をトップが示し、失敗しても、変革行動を評価する仕組みを会社が作っていくことが必要なのだ。
その上で、マネージャーがすべきことは、「組織の外のまだ見えていない事業機会との橋渡し」だという。
「部下の意見を聞き、関係を構築するだけでは、成果にはつながりにくいのです。リーダーが組織の外にニーズやシーズを見極めて明示した目標にメンバーが向かう際、マネージャーはチームのダイバーシティとつなげていかすことが重要で、そこにイノベーションを起こし、成果をもたらすヒントがあります。いかに外部環境に対して強みを発揮できるかによって、成果が出せるかが決まる。目の前にいる人材のモチベーションやエンゲージメントを上げることだけに注力しても、外界と結びついた成果が無ければ、達成感も無く部下も飽きてきます」

テンションを避けるとイノベーションは生まれない
パラドクスを内在させることができる組織は持続可能と言われるなか、日本ではパラドクスに目を向けないか、入れないようにしていると谷口教授は危惧する。
「日本に多いのは、なんとなく『みんな仲よし』。メンバーの多様性に目を向けず、コンフリクトを避ける。同質性のなかで協働する状態です。テンション(緊張)を許容し、組織の中でどれだけ新たな解決策を作れるかが重要なのです」
論争・衝突を意味するタスクコンフリクトは、プラスの面を活性化させるマネージメントが必要だという。
「A~Dさん全員に意見を求めて『Aさんの意見にしよう』と決めるだけでは、個人の意見以上のものは生まれませんし、上司の一存では、次回からAさん以外は積極的に発言しなくなってしまいます。意見を出すだけでなく、異論をぶつけ合い、AでもBでもCでもDでもない『X』という結論に至れること。それをまだ可視化されていない組織外の事業機会につなぎ、変革の成功体験につなげていく。それが、ダイバーシティ&インクルージョンの強さであり面白さなのです」
もちろん、好き勝手に意見を出すだけでは「X」にはたどり着けない。マネージャーが明確な目的やゴールを示すことで、参加者は建設的な意見を出し合い、異論をぶつけ合うことができる。そしてどこにも無かった結論に到達できたことを評価することが、ダイバーシティをビジネスにいかす第一歩になる。
マネージャーの多くは、部下を理解しようとしていても、多忙なあまり自分の深層のダイバーシティに目を向けられていないかもしれない。だが、自身もチームのなかの多様性の一人。そこに気が付くことこそが、多様性をいかした組織運営につながり、イノベーションを起こせるようになっていく。
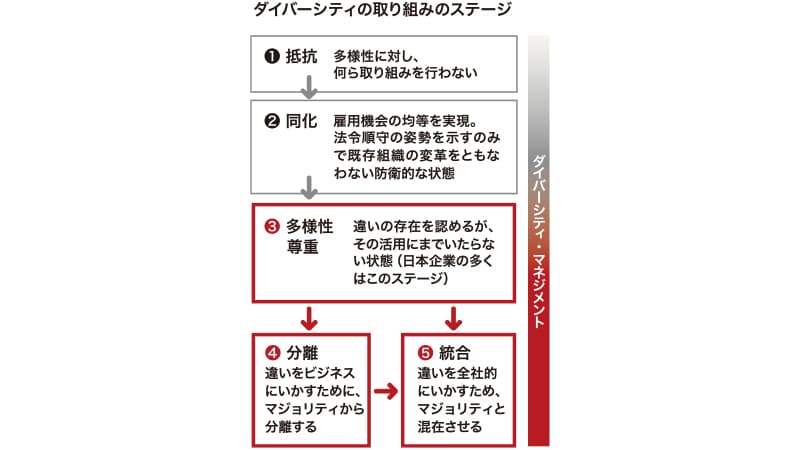
※所属・役職等は取材時のものです。


- 早稲田大学 商学学術院 大学院商学研究科 教授谷口 真美(たにぐち まみ)
-
1996年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了、博士(経営学)取得。広島経済大学経済学部経営学科助教授、広島大学大学院社会科学研究科助教授を経て、2000年より米国ボストン大学大学院組織行動学科・エグゼクティブ・ラウンドテーブル客員研究員。2003年より早稲田大学助教授(准教授)。2008年より現職。2013~2015年にはマサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院研究員。著書に『ダイバシティ・マネジメント―多様性をいかす組織』(白桃書房)があり、新著も企画中。
記事検索キーワード
VOL.47その他の記事
-
 特集目の前のものを全力で好きになる。山田五郎さんに学ぶ仕事への向き合い方
特集目の前のものを全力で好きになる。山田五郎さんに学ぶ仕事への向き合い方 -
 VOL.47ありふれたものから共感と感動を。「見立て」の文化を担うミニチュア写真家が見据える世界
VOL.47ありふれたものから共感と感動を。「見立て」の文化を担うミニチュア写真家が見据える世界 -
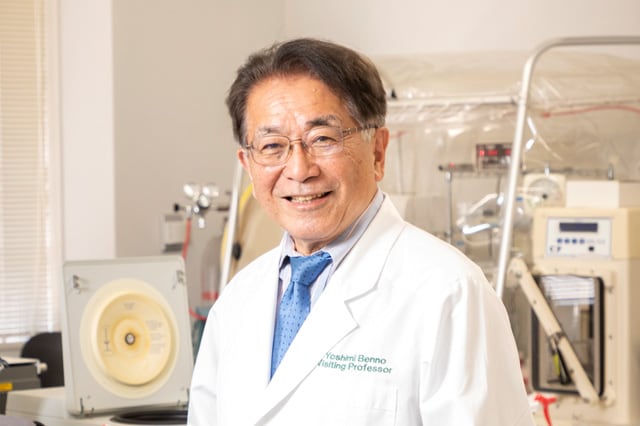 VOL.47人々の健康を守る腸内フローラ 前例のない研究に挑戦する研究者を支えた「予言」
VOL.47人々の健康を守る腸内フローラ 前例のない研究に挑戦する研究者を支えた「予言」 -
 VOL.47みんなのため、そして地域のため
VOL.47みんなのため、そして地域のため
先端技術で目指す病院の姿 -
 VOL.47培養肉で食糧危機に挑む 再生医療と3Dプリント技術で目指す、持続可能な食の未来
VOL.47培養肉で食糧危機に挑む 再生医療と3Dプリント技術で目指す、持続可能な食の未来 -
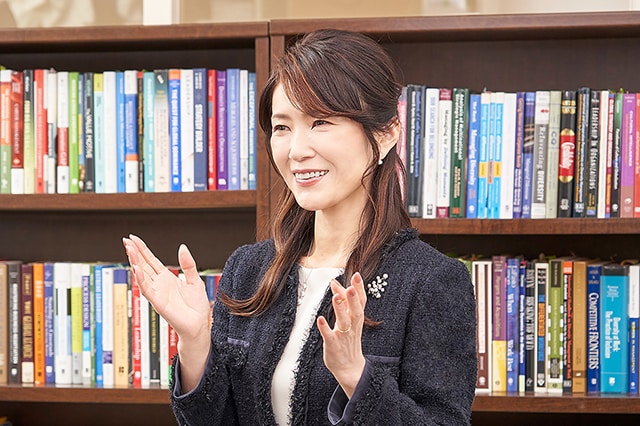 VOL.47深層のダイバーシティと向き合うことでイノベーションを生み出す組織になる
VOL.47深層のダイバーシティと向き合うことでイノベーションを生み出す組織になる -
 VOL.47すべては、夢から始まる。島津製作所が目指す人と地球の健康
VOL.47すべては、夢から始まる。島津製作所が目指す人と地球の健康 -
 VOL.47世界トップクラスのシェアを誇る島津製作所の「産業用ターボ分子ポンプ」チームの結束力とプライド
VOL.47世界トップクラスのシェアを誇る島津製作所の「産業用ターボ分子ポンプ」チームの結束力とプライド -
- NEWS & TOPICS2022年2月~6月
-
- 2022.2.2遺伝子解析装置AutoAmp™ 第40回日経優秀製品・サービス賞の日経産業新聞賞を受賞
- 2022.3.9/3.22/5.12健康経営や女性活躍推進、働きがいのある会社として
- 2022.4.13/4.27「レッドドット賞」と「iFデザインアワード2022」を受賞


