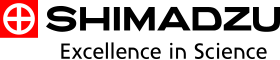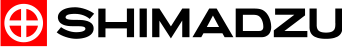テラヘルツ波のシグナル可視化を実現
テラヘルツ波は、次世代通信や非破壊検査など様々な利用が期待され、近年活発に研究が進められています。理化学研究所 光量子工学研究センター テラヘルツ光源研究チームは、長年の悲願だった手のひらサイズのテラヘルツ波光源の開発に成功しました。一方で光源開発と並行して進められていたテラヘルツ波検出の研究においては、実験の成否を決めるシグナルの測定に難航していました。そんな状況を打破し、テラヘルツ波の検出実験の成功に貢献したのが「レーザースペクトラムアナライザSPG-V500」です。研究チームを率いる南出泰亜チームディレクター、そして、研究を主導したディーピカ ヤダフ研究員、瀧田佑馬研究員に当時のお話をお聞きしました。

南出泰亜チームディレクター(右)、ディーピカ ヤダフ研究員(中央)、瀧田佑馬研究員(左)
理化学研究所 光量子工学研究センター テラヘルツ光源研究チームの研究室にて
25年の悲願、手のひらサイズのテラヘルツ波光源の完成
テラヘルツ波とは、電波と赤外線の間の周波数領域(100 GHz(=0.1 THz)~10 THz程度)にある電磁波です。物質を透過しやすく、直進性も高い一方で、X線と異なり生体組織を破壊することがないといった特性から、通信、医療、検査などの各種分野への活用が長らく期待されてきました。しかし、汎用性のある光源(発生装置)と検出器の開発が難しく、いまもまだ、広い実用化には至っていません。
実用的なテラヘルツ波光源の開発を目指し、長きにわたって研究を続けてきたのが、理化学研究所の南出泰亜さんです。テラヘルツ波がマイナーだった時代から研究に着手して25年以上。ついに手のひらサイズで高出力のテラヘルツ波光源の開発という悲願を果たし、2024年9月に完成を公表しました(図1)。南出さんは話します。
「テラヘルツ波を発生させる方法はいくつかありますが、私たちが研究してきたのは、非線形光学結晶(※1)と呼ばれる結晶にレーザー光を照射して、その際の波長変換によってテラヘルツ波を得る方法です。その出力を十分に高める方法がないかと長年研究してきた結果、出力を一気に10万倍にする方法を見出し(※2)、さらに研究を重ねた末にようやく、コンパクトで高出力のテラヘルツ波光源を完成させることができました」。

図1 手のひらサイズのテラヘルツ波光源ⅰ
提供:理化学研究所
光源と対をなすテラヘルツ波の検出とは
一方、光源開発と対を成すのがテラヘルツ波の検出方法の開発です。検出方法自体はすでに複数あるものの、テラヘルツ波の中でも周波数の低いサブテラヘルツ波を室温で高感度に検出するための汎用的な方法はなく、実現が求められており、この研究にSPG-V500が使われました。 検出方法の開発の道筋は、光源開発を進める中から見えてきたと南出さんは言います。
「私たちが開発したテラヘルツ波光源は、簡単に言えば、レーザーの光をテラヘルツ波に変換する装置です。検出というのはその逆、つまりテラヘルツ波を光に戻せばいいのであり、光源開発で得た技術を用いれば、望んでいた検出方法も実現できるはずだと考えました」。
検出の原理は、次のようになります(図2)。まず、ポンプ光(=レーザー光)とテラヘルツ波を、同時に非線形光学結晶に入射させます。すると、ポンプ光とテラヘルツ波の周波数を足した周波数を持つ光(=sum frequency generation, SFG, 和周波発生)と、両者の差にあたる周波数を持つ光(=difference frequency generation, DFG, 差周波発生)が、波長変換によって発生することが理論的に分かっています。つまり、SFGとDFGの2つの光が出てきたことが観測できれば、テラヘルツ波が入射したということが確かめられます。 この原理に沿って、テラヘルツ波検出の研究が進められました。

図2 非線形光学結晶を用いたテラヘルツ波検出の原理
困難を極めたシグナルの検出
テラヘルツ波検出の研究を担当したのは、研究員のディーピカ ヤダフさんです。
「研究の目的は、BNAという有機非線形光学結晶を用いて、サブテラヘルツ波、すなわち、1THzより周波数の低いテラヘルツ波の検出を実現させることでした。有機非線形光学結晶を用いたテラヘルツ波の検出自体はすでに行われていたものの、これまでは、1THz以上の周波数帯の検出しか行われていません。サブテラヘルツ波の検出を試みることには大きな意義がありました」。
ヤダフさんは、光源開発の中心メンバーである研究員の瀧田佑馬さんにも相談しながら、ゼロからサブテラヘルツ波検出の研究をスタートさせ、数カ月かけて検出光学系を作り上げました(図3)。
PPLNという非線形光学結晶を用いて発生させたテラヘルツ波とポンプ光が同軸上にある状態でBNA結晶へと入射させると、先に紹介した原理から、BNA結晶を通過した光の中にSFGとDFGが含まれるはずです。そのシグナルが検出できれば、テラヘルツ波が検出できたことになります。

図3 ヤダフさんらが構築したサブテラヘルツ波検出のための実験装置の概略図
提供:理化学研究所
数々の実験を経て、SFGとDFGのシグナル検出段階へと至ったものの、検出は困難を極めました。その難しさこそが、サブテラヘルツ波の検出が行われてこなかった理由です。その点についてヤダフさんはこう話します。
「私たちの実験で検出すべきSFGとDFGのシグナルは、強いポンプ光と同軸上に出てきます。つまり、両者は混ざっています。その上、シグナルとポンプ光との波長の違いはサブテラヘルツ波のエネルギー分だけのため、極めてわずかです。ポンプ光の波長が約1064 nmなのに対して、検出したいシグナルは1062 nm(SFG)と1066 nm(DFG)ほどなのです。加えてポンプ光はとても強力なのに対して、シグナルは極めて微弱。かつそれらはパルス光であるため、シグナルは瞬間的にしか発生しません。まるで海に混ざった一滴のインクを探すようなものでした」。
ヤダフさんたちは様々な工夫を重ねます。ポンプ光を弱めるためにフィルターを入れ、シグナルだけを分離するために回折格子を挟み、調整を繰り返し、何度も測定を行いましたが、シグナルは検出できませんでした。もしかしたら、そもそもシグナルが出ていないのかもしれない。理論上は出るはずでも、実験のどこかに間違いがあるのかもしれない。そんな気持ちすら沸いたと言います。どうすればいいのか――。みな途方に暮れていたところ、一通のメールが南出さんの目に留まりました。
姿を現すシグナル 「やった、見えた!」
「2023年の年末のことでした。受信メールに「レーザースペクトラムアナライザ SPG-V500」の紹介があり、『リアルタイム測定』という言葉が目に入りました。それを見て、「もしかして」と思ったのです」と南出さんは振り返ります。
2024年の年明けにはデモ機を取り寄せ、使用してみました。ヤダフさんと共に実験をしていた瀧田さんがその時の様子を話します。
「大体の調整を行って、ひとまず測定してみたところ、微弱ながらもそれらしいシグナルがすぐに見えました。「もしかしてこれは!」と思いました。ただ、レーザーがパルスのため、タイミングも合わせないといけないし、実験装置の空間的な調整も必要で、正確な測定にはしばらく時間がかかりました。全ての調整を終えて改めて測定すると、シグナルがグググーッと伸びたんです。間違いありませんでした。求めていたシグナルでした(図4)。それを見た時、みな声を上げました。「やった、見えた!!」って」。

図4 近赤外領域へ波長変換したサブテラヘルツ波の信号を示すスペクトル
SPG-V500にて測定。左右の2つのピークが求めていたシグナル(左がSFGで右がDFG)。
中央のピークはポンプ光。サブテラヘルツ波を入れない時は、左右の2つのピークは出てこない。
提供:理化学研究所
シグナル検出を実現したSPG-V500の特長とは
なぜSPG-V500であればシグナル検出できたのか。他の光スペクトラムアナライザとは何が違ったのか。 一番の要因は、本機の特長であるアレイセンサによるリアルタイム測定です。多数のセンサによって一定範囲のスペクトルを同時に測定できます。対して、スキャン式の光スペクトラムアナライザの場合、波長ごとに順次スキャンして測定するため、パルスレーザーを用いる本研究においては、パルス光が届く瞬間に合わせてスキャンしていなければならず、タイミングを合わせるのが極めて難しかったのです。SPG-V500のリアルタイム測定であれば、瞬間的にしか現れないシグナルも無理なく測定することが可能です。
また、SPG-V500はマルチモードファイバ入力で約0.02 nmという高分解能測定が可能であるため、極めて弱い今回のシグナルを捉えることができました。
ヤダフさんは、SPG-V500を使用した感想をこう話します。
「SPG-V500のリアルタイム測定は、検出を実現してくれただけでなく、測定そのものを本当に楽にしてくれました。従来は周波数ごとに位置を微妙に調整しながらシグナルを確かめなければならなかったので測定に膨大な時間がかかりましたが、SPG-V500ではそんな作業は一切不要で、容易に検出できました。また、マルチモードファイバの場合、通常は分解能が低くなるのですが、SPG-V500は高い分解能を維持したままで、多くのシグナルをカップリングできました。とても弱いシグナルの検出が可能になったのは、そのおかげでした」。
レーザースペクトラムアナライザSPG-V500の製品ページへ

図5 レーザースペクトラムアナライザSPG-V500
理化学研究所 光量子工学研究センター テラヘルツ光源研究チームの研究室にて
検出技術の先には、新たな量子研究の世界も見えてくる
ヤダフさんは、この成果を2024年9月にオーストラリアで行われた「赤外ミリ波テラヘルツ国際会議(IRMMW-THz 2024)」にて発表し、大きな反響を得ることになりました。実用化への道のりはまだ決して平坦ではありませんが、テラヘルツ波の検出において新たな可能性を切り拓くことになりました。そしてこの研究の先にあるのは、検出器の開発にとどまりません。突き詰めていけばさらに別の世界が見えてくると、ヤダフさんは話します。
「今回の研究では、シグナルをより明確にポンプ光から分離できるようにすることがまだ課題として残っています。その点を改善させていくことは、つまり、テラヘルツ波の検出感度を上げていくということですが、それを極限まで高めていき、テラヘルツ波の光子を1つ単位で検出できるという段階にまで近づいていくことが可能になれば、テラヘルツ波による新しい量子研究の世界が見えてくると考えています。そんな未来も意識しながら、この研究をさらに発展させていきたいです」。
- ※1 非線形光学結晶:入射する光に対して非線形な応答をする結晶で、レーザー光の波長を変換するのに用いられる。様々な非線形光学結晶がある中で、従来広く使われてきたのは無機のもの。南出さんのチームが開発した光源に用いられたPPLN(periodically poled lithium niobate)も無機である。一方、本文中で言及されるBNA(N-Benzyl-2-methyl-4-nitroaniline)は有機であり、非線形光学定数が無機のものに比べて大きいため、幅広い周波数帯のテラヘルツ波の発生および検出に有効である。
- ※2 南出さんらは、光源の開発自体は2000年代には実現していたが、装置は大きく、出力は小さかった。実用的なものにするには、装置は小さく、出力は格段に上げる必要があった。結晶にレーザー光を入射することで生じる散乱光(=誘導ラマン散乱)の中にテラヘルツ波を見いだそうとしていたが、実はその光が、結晶中の粗密波で生じる別の散乱光(=誘導ブリルアン散乱)に阻害されているのかもしれないことを、過去の実験ノートの記述によって気付く。それならばと、誘導ブリルアン散乱を除去してやると、誘導ラマン散乱が大きくなり、出力は一気に10万倍になったという。
参照資料
| ⅰ | 2024年9月6日 理化学研究所 プレスリリース「手のひらサイズの高輝度テラヘルツ波光源を開発 -実用上の多様な非破壊検査対象に道筋-」 https://www.riken.jp/press/2024/20240906_1/index.html |
| ⅱ | Deepika Yadav et al.:Sub-Terahertz Wave Detection Using Frequency Up-Conversion in Organic BNA Crystal, The 49th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves(IRMMW-THz 2024) |
関連リンク
改善事例:シングルモードレーザーにおけるサイドモードの挙動検出
SHIMADZU TODAY 未開の電磁波「テラヘルツ波」の研究に島津の光スペクトラムアナライザが貢献