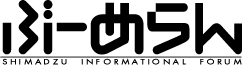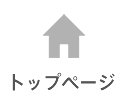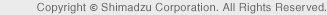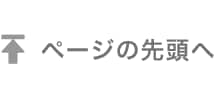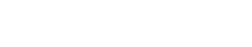 Backnumber
Backnumber
島津遺産
鉄の色
高度経済成長をけん引してきた鉄鋼業。その発展を支えたカントレコーダは、品質を見極める目だった。
鉄は国家なり
「鉄は国家なり」と語ったのはプロイセン王国、ドイツの宰相ビスマルク。その言葉通り、近代、鉄鋼の生産量は国力の重要な指標だった。鉄は、大半の機械部品に使われ、鉄道レール、鉄筋や鉄骨などインフラの資材にもなる。鉄鋼業は、まさに近代国家の根幹を形づくってきたのだ。そのため、世界中どこでも、鉄鋼産業は政府の肝いりで進められた。
日本の近代鉄鋼業も、始まりは国家主導だった。1901(明治34)年、殖産興業、富国強兵を標榜する政府は、官営八幡製鉄所を設置。高さ30メートルを超える溶鉱炉「高炉」は、近代化の象徴となった。
製鉄所に持ち込まれた鉄鉱石は、まず高炉で製錬されて粗製の鉄「銑鉄」が取り出される。次に銑鉄は転炉と呼ばれる溶鉱炉に入れられ、精錬によって純度を高められ、鋼となる。これを型に流し込んだ後、ローラーで圧延して鉄板やパイプ、鉄筋といった製品に加工し、出荷される。八幡製鉄所の建設にあたり、政府は高炉や転炉などの技術を海外から導入。鉄鋼の国産化を目指したが、事故やトラブルが相次ぎ、当初は生産量が伸び悩んだ。 だが、次第に技術を高めると、全国に製鉄所が続々と開業。軍需の拡大を背景に生産量は一足飛びに増え、太平洋戦争が勃発した1941(昭和16)年のピーク時には年産800万トン超にまで達した。
しかし戦禍を被り、日本の鉄鋼生産設備はほぼ壊滅。わずかに残った施設も老朽化が激しく、しかも石炭や鉄鉱石の輸入もままならなかった。

転炉での作業風景。2000℃を超える高温の高炉内で製錬された銑鉄は、炭素やリンなどの不純物を含むためもろい。そのため、不純物を取り除く転炉での作業は、鉄鋼の品質を決める重要な工程。高炉から運ばれた銑鉄に再利用する鉄スクラップを加え、高圧の酸素を吹き込むことで酸化反応を起こし、不要な炭素やリンなどを取り除く。さらに二次精錬という最終的な成分調整を経て、鉄鋼が精製される。
品質を安定させられないか
朝鮮戦争が始まると特需が発生。日本の鉄鋼産業は壊滅的な状況から息を吹き返す。1954(昭和29)年には高度経済成長も始まり、日本中に復興の槌音が響き渡る中、鉄鋼需要は天井知らずで伸び続けた。それに応えるため各地に高さ30メートルを超える高炉が林立し、最新技術を導入した転炉も続々と建設された。
そんな中、大量生産、効率化のネックとなっていたのが、転炉の精錬工程における品質管理だった。鉄鋼の硬度や特性は主に5つの元素、炭素、ケイ素、マンガン、リン、イオウの含有率で変わる。それを決めるのが炉内の温度や、吹き込む酸素の量で、その品質をみるためには精錬中の炉内の鉄鋼の成分をすばやく分析し、炉の制御にフィードバックする技術が必要とされていた。しかし、1950年代中盤に主流だった化学分析では、4元素の測定に40分以上も要し、その間に鉄鋼の品質はばらついてしまわざるを得なかったのだ。
そこで注目されたのが、カントレコーダである。分析する試料を火花放電させ、試料から発せられた光を分光器で分散することで出るスペクトル線(光を構成する波を波長の順に並べたもの)の強度を測定する。元素はそれぞれ固有の波長を持っているため、スペクトル線を観測すればその種類と量を判別できるのだ。多元素を同時に測定でき、測定に要する時間もわずか2分ですんだ。
鉄鋼業界の熱い要望と支援
実をいえば当時、アルミなどの軽合金の製造では、すでにカントレコーダが品質管理の主役として活躍していた。だが、軽合金の組成は、大気中で測定しても問題がなかったのに対し、鉄鋼では、空気中の酸素が炭素やリン、イオウといった重要な元素のスペクトル線を吸収してしまい、必要な元素を正確に測定できなかったのだ。
分光器をなんとか真空下に置き、不活性ガス中で鉄鋼試料を放電させることができないか。高まる鉄鋼業界のニーズを感じ取り、島津が開発を始めたのは1957(昭和32)年。当時、世界でもまだ一社が先行して開発したばかりで、有効な文献もないまま手探りでのスタートだった。
開発をスタートして2年近くが経った1959(昭和34)年の初めには、取り組みを聞きつけた製鉄所から島津へ注文が舞い込んだ。製品になる目処がまだついてない時点での受注など異例中の異例。それほど世の中から熱望されていたことを示す逸話だ。
翌1960(昭和35)年3月には、技術者らの努力と、関係者の後押しを受け、国産第一号の真空型カントレコーダ「GV-100型」が完成。以後、製鉄所へ続々と納入されていった。
もっとも、電子回路が洗練されていなかった当時、故障も多く、納入後も改善は続いた。対応に技術者がかり出され、製鉄所に常駐することもしばしばだったという。技術者にとっては重責を負うことにはなったが、現場のリアルな状況を知り、要望を吸い上げるまたとない機会ともなった、と当時を知る技術者は振り返る。
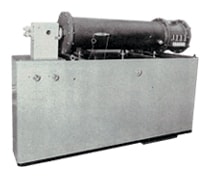
1960年代の真空型カントレコーダ
GV-100型(分光器本体)
鉄がこの世にある限り
その後も製鉄所と島津は連携しながらカントレコーダの改良を続け、小型化や、測定時間の短縮、分析精度のさらなる向上を実現し、1980年代には島津製カントレコーダの国内シェアは90%を超えるまでになった。その頃、日本の鉄鋼生産高は、年間1億1千万トンで世界第1位。品質においても日本の鉄鋼メーカーの名は世界的なブランドとして認められるまでになっていた。その功労者としてカントレコーダを推すことに、異が唱えられることはないだろう。
今日、カーボンファイバーなど新素材が続々と登場したが、低コストで加工性の高い鉄は依然として工業原料の王者として君臨している。カントレコーダは進化し、PDAという名の装置に変わり、活躍の場を中国やインドにも広げた。その性能向上に向けた改良は、その後を引き継いだ技術者たちによって、日々続けられている。