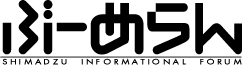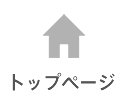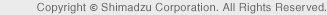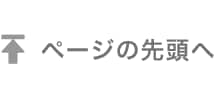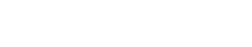 Backnumber
Backnumber
ジュー ル・ヴェルヌの見た夢

サイエンス・フィクションは、単なる絵空事ではなく、想像と科学の間を線でつなぐ、重要な役割を果たして来たのかもしれない。
SFの父といわれるジュール・ヴェルヌが何を想像し、科学技術はそれにどう応えたのか。
その軌跡は、未来を占う鍵となるかもしれない。
科学の世紀に生まれて
「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」
19世紀のSF作家ジュール・ヴェルヌが語ったとされる言葉だ。
19世紀は「科学の世紀」とも呼ばれ、今日の豊かな生活を支える科学技術がいくつも発明された。電気を扱う技術や、自動車のエンジンの発明、医療に欠かせないX線の発見もこの時代だ。こういった科学のもたらす恩恵にインスピレーションを得て、未来へのイマジネーションを物語にしたのが、ジュール・ヴェルヌだったのである。
ヴェルヌが生まれた1828年、人々の目は空へと向いていた。当時、すでに気球は登場していたが、見せ物や愛好者の娯楽の域を出ていなかった。それを、山岳地帯やアクセス困難な地域、諸大陸をすばやく移動する手段へと変え、大空を我がものとすることを夢見ていたのだ。
数々の冒険家が気球での冒険に挑戦したが、進路をコントロールする手段がなかったため、遭難の憂き目に遭うことも少なくなかった。そのため、気球を自由に操る技術の開発がこぞって行われていた。
想像の翼を広げて
1863年、35歳のヴェルヌが書いた最初の長編小説『気球に乗って五週間』でも、気球を使ってナイル川の源流探索へ出発するイギリス人が描かれている。先進的だったのは、気球に充填した水素ガスを膨張させて上昇したり下降したりする装置を作品の中で"開発"し、気球をある程度自由に操ることができるようにする方法を示したことだった。しかし、その小説の中でも気球の進む先は風のみぞ知るもののままだった。
この気球の不自由さは、1860年代の航空学の議論を反映したものだった。もはや気球を自由に操るという関心は次第に薄れ、人々の興味は操縦可能な推進用スクリューを備えた飛行船へと移行しつつあった。その一方で、後の飛行機につながる「空気よりも重いものを飛ばす」という考え方も生まれていた。この時、鳥を模した珍妙なものから、後の飛行機につながるものまで数々の機械が考案されたが、もっとも見込みがあると考えられていたのは、巨大なローターを持つヘリコプターであった。そのヴィジョンはヴェルヌ、1886年の作品『征服者ロビュール』に登場したアルバトロス号の空の旅というイメージで具現化されている。
想像に追いついた科学技術
ヴェルヌが想像した、人がいつか機械的な力で鉄の塊を空へ自由に飛ばす日は、それから20年足らずで一気に現実へと近づいた。1903年にはライト兄弟が飛行機の有人飛行に成功。さらに1937年には、初めて飛行できるヘリコプターが登場する。
空への関心とともに人々は宇宙への興味を募らせていた。その思いは、天文学や天体力学を発達させ、ヴェルヌも宇宙への旅を夢想した。
もっとも身近な天体・月への冒険が記された1865年の『地球から月へ』では、巨大な砲弾で月へ向かうという一見とんでもない方法ではあるものの、初めて地球の重力を運動エネルギーで超える方法が、弾道計算まで詳細に伝えられた。
月へ行くというこの作品のイメージは、20世紀に宇宙を目指す者の道標となった。宇宙工学の功労者フォン・ブラウンや1968年に人類で初めて月の周回飛行を成功させたアポロ8号の乗組員フランク・ボーマンは、「幼き日にヴェルヌの作品を見て影響を受けた」と明言しているほどだ。
ヴェルヌの先へ
19世紀の後半、ヴェルヌが人気作家としての地位を築いていた頃、日本は、明治の産声とともに、欧米の文物が大量に入ってきた。その一つに、ヴェルヌの作品もあった。『気球に乗って五週間』を読んだ人々は、空への夢をふくらませていたことだろう。
島津製作所の初代島津源蔵も、もしかしたら読者であったかもしれない。創業から2年後の1877年には、科学教育普及のために、日本初の有人軽気球飛揚に成功している。まさに想像を実現させたのだ。
それからも科学技術の発展は、ヴェルヌの見通したヴィジョンを次々と実現させてきた。もちろんロケットの推進方法やデザインはヴェルヌの設計どおりではないが、"目的地"へは続々と到達し、もはや人類未踏の場所は、地球の内には地底や海底の奥深くしか残されていない。
そして地球を越え、月を越えた先、誰も見たことがない宇宙の深淵への"冒険"もすでに始まっている。
ヴェルヌの想像を超えた先には何が待っているのか。それを解き明かし、あるいは到達するための科学技術を生み出すのは、我々の想像力なのかもしれない。