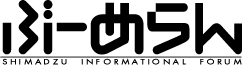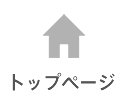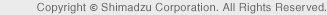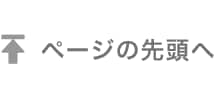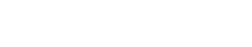 Backnumber
Backnumber

「日本の行く末」
田原 総一朗

イギリスの産業革命から100年後の明治時代、圧倒的な技術力、国力の違いに、目を覚めさせられた新生日本は、大急ぎで近代国家への道を歩み始めた。その後100年で、日本は遅れを挽回するどころか、世界トップレベルの工業力を誇るに至った。その進歩の背景にあったのは「民の力」、とジャーナリスト田原総一朗氏は指摘する。
和を以って貴しとなす
明治以降、日本が急速に発展できた背景を探っていくと、聖徳太子に行き当たります。
十七条の憲法の最初に記された「和を以って貴しとなす」。これは旧来からあった神道を信奉する一派と、勃興しつつあった仏教勢力が、いがみ合うことなく、力を携えて事に当たっていこうと説いたものです。ある宗教を信奉する国に、新たな宗教が入ってくれば、世界中どこでも争いが起こります。21世紀の今に至るも、多くの争いのもとを辿ると宗教がある。ところが、聖徳太子は国民が仲良くすることこそ最大の目的であって、宗教などは柔軟にアレンジすればよいと考えた。これがその後の日本を特徴付ける精神となったのです。
外来の文化を拒絶することなく柔軟に受け入れ、自分のものにしていく。文字も、工芸も、建築も、みんなそうです。この極めて柔軟な思考が、「和魂洋才」というスローガンになって幕末にも発揮された。精神は変わらず持ち続けるが、技術は積極的に取り入れる。頭の切り替えを最小限で済ませられたからこそ、技術導入が急速に進んだのです。
加えて、識字率が高かったことも幸いした。江戸時代末期、寺子屋教育が広まっていたこともあって、江戸府内の識字率は70%を超えていたともされます。技術書やマニュアルが読めれば、技術の習得も早い。まさに水がしみ込むように技術が浸透していったわけです。
1877年(明治10年)の西南戦争は、ともに維新の立役者である西郷隆盛と大久保利通の戦いで、大久保利通が勝った。これは日本の行く末を決める大きな分岐点でした。明治政府は富国強兵をスローガンに殖産興業を進めていましたが、西郷は軍事を優先、大久保は産業を優先する立場だった。ここで西郷が勝っていたら、現在の日本は今とはだいぶ違った形になっていたでしょう。
主役は民
本題はここからです。
殖産興業を進める明治政府は、官営工場を矢継ぎ早に開設した。外国人のエンジニアを雇い入れて、最新の技術を導入。国の主導で産業を興そうとしたのです。ところが、西南戦争での財政難もあって、政府は1880年頃からこうした工場を次々に売りに出してしまう。
これがよかった。
産業の推進役から官が退いて、民が主役となった。多くの産業で官の独占が崩れ、民間企業が互いに競争する構図になったのです。一つでも多く売りたい民間企業は、当然サービス合戦を繰り広げる。顧客の要望をできる限り聞いて、それに応えられる製品を作ろうとする。その結果、技術力が高まって、良い製品を作れるようになる。産業が発展し、ひいては国の発展に結びついた。急速な発展を実現できたのは、まさに民間の力があったからこそです。
災い転じて
戦後、日本の発展は加速度を増し、1980年代には「ジャパン・アズ・ナンバー・ワン」と世界から羨望の目で見られることになります。発展の要因はいくつもあったでしょうが、僕は、2つの大ピンチの克服があったことを挙げておきたい。
一つは、敗戦です。都市は空襲で焼け野原となり、日本は経済的にも精神的にも壊滅的なダメージを受けた。工業地帯も更地になった。復興を目指す企業は、ここで最新の機械設備を導入することになったわけです。欧米の企業が古い工場を持て余していたときに、いち早く最新設備で最先端のものづくりを実践できた。これは、大きかった。敗戦によって、軍隊がなくなり、優秀な人材が産業分野へ移行したこともアメリカにはできなかったことです。
こうして高度経済成長が始まった。日本中に工場が立ち並び、各社は競争を繰り広げ、より良いものを大量に安く作ることを目指した。そして、60年代には公害列島というありがたくない名前で呼ばれることになった。民衆の怒りは頂点に達し、行政も経営者も、本気で公害の克服を目指すことになった。その結果、日本は、見事に公害克服先進国となることができた。産業の発展と人々の安全な暮らしを両立できたことで、持続的な発展に道筋を付けることができたのです。
失敗を恐れない勇気を
さて、現在の話です。
高度経済成長はとっくに終わり、モノ余りの時代となって、良いものを作っても、売れないという時代が続いています。
そこでどうするか。
売れないからといって、商品の価格を下げた企業はどんどんじり貧に陥っています。悲観論も飛び交っていますが、僕は、こんなに面白い時代はないと思っています。
ネットの番組で若い経営者との対談をよくやっていますが、彼らのアイデアやバイタリティは、明治維新や戦後のベンチャー経営者にも決して劣らないものがあります。そして何より彼らは、自分のやろうとしているビジネスが、社会に貢献できるかという視点を持っている。
大切なのは付加価値を付けることで、誰にもまねできない、そして人に喜びを与える製品やサービスが生まれる土壌は十分にある。あとは、それに向けてチャレンジをするだけです。
当然、チャレンジには失敗がつきものです。しかし、失敗することで自分の頭で考え、また新しいチャレンジにつなげることができる。企業は上から言われたことをやっているだけの社員をつくるのではなく、チャレンジを怖がらない社員を育てるべきです。それができる企業が、21世紀を引っ張っていくことになるでしょう。
未来は明るい。僕はそう信じています

ジャーナリスト
田原総一朗氏
1934年、滋賀県生まれ。60年、早稲田大学卒業後、岩波映画製作所に入社。64年、東京12チャンネル(現テレビ東京)に開局とともに入社。77年にフリーに。テレビ朝日系『朝まで生テレビ!』『サンデープロジェクト』でテレビジャーナリズムの新しい地平を拓く。98年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ城戸又一賞を受賞。 現在、早稲田大学特命教授として大学院で講義をするほか、「大隈塾」塾頭も務める。