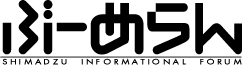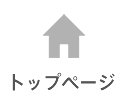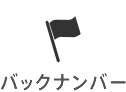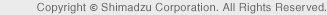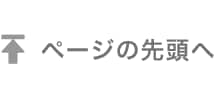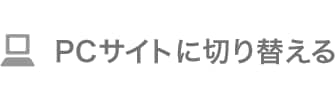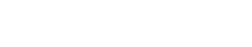 Backnumber
Backnumber
日本一の大型構造物試験機が支える大きな安心
都市の耐力測定機

日本大学理工学部には日本一の、世界でも最大級の30MN(メガニュートン)大型構造物試験機(縦型)がある。多くのビルや橋が建設前にここで強度をテストされ、安全性が高められてきた。製造から35年を経て今なお現役。国内外から試験の申し込みが絶えることがないという。
そびえ立つビルのような装置
長さ約22メートル、重量約30トンの柱4本が天井を支えるようにそそり立ち、 耐圧盤を取り付けた鋼鉄の床をとり囲む。日本大学理工学部には、地上6階、 地下3階に相当する大型構造物試験機があり、まるで、むき出しのエレベーターのような威容で見る者を圧倒する。
アラームの音がこだまし、旋回灯が壁を黄色に染めると、耐圧盤がゆっくりと台座に向かって下降を始める。 台座の上に試験材料として据えられているのは短いコンクリートの柱。高さ約1メートル、 周囲は大人の両腕でようやく抱えられるほどだ。 コンクリート柱の上面にたどり着いて一瞬動きを止めた耐圧盤は、 なおも手を緩めることなくコンクリート柱に力を加えていく。 数秒の後、コンクリート柱は建物をふるわせ、轟音とともに中心からくだけ散った。
この大掛かりな装置があるのは、大型構造物試験センターだ。 他にも地震のさまざまな揺れを再現できる 多入力振動試験装置や構造物疲労試験機など島津製作所製の大型装置が導入されている。 大学としては最大規模の施設だ。
「センター内部の諸施設の設置にあたり、 どんな装置を導入するかの議論のなか、他にも導入されている身近な設備ではなく、 自分たちの研究に本当に必要なものを導入したいと主張しました」
と、当時を振り返るのは理工学部海洋建築工学科の安達洋教授。 当時助手だった安達教授が、世界最大級の装置導入時を熱く語った。
大型構造物の安心・安全のために
この装置には、日本のみならず世界の構造物の安全性を高めるという誇るべき仕事がある。 ダムや橋りょう、高速道路、高層ビルなどに使われる部材や数分の1の縮小モデルが持ち込まれ、 つぶされたり、引っ張られたり、曲げられたりして、強度を試されてきた。 ここで得られたデータは、より安心・安全な構造物の設計と施工に確実に生かされている。
同じように構造物を対象とした試験機はいくつか存在するが、 縦型で最大30メガニュートン(約3000トン)もの圧力を加えられるだけでなく 「引張」「曲げ」まで載荷が可能な装置は、大学としては唯一で、 国内では後に(独)土木研究所に導入されたものしかない。いずれも島津製だ。
「そのころ、ビルなどの耐震壁をそのままのサイズでテストできるところは、ありませんでした。 この装置が導入されたとき私はまだ学生でしたが、夢のような話だと胸躍らせたものです」
安達教授とともに、この試験機で構造物の研究を行う中西三和教授は、熱っぽく語る。
大きくなければ確かめられない
大型構造物試験機が同学部に導入されたのは1975年。 建築基準法が大幅に改正され、超高層ビルが続々と建設されているさなかのことだ。 ビルに限らず構造物が造られる際には、安全性を確保するため、設計者は理論上の計算を何度も繰り返し、 建設に移る前には、模型を作って、幾度となく強度試験を繰り返す。だが、模型はあくまで模型であり、 実際の構造物が地震などの強い衝撃を受けたときにどのような挙動を示すかは、類推できない場合も多い。
解決法は、できれば実物大の、 あるいは同じモデル実験でもできるだけ実物大に近いサイズで実験することでしか得られない。 試験機も自ずとそれに見合った大型サイズが求められた。
数々の試験機を開発してきた島津製作所にとっても、これほどのサイズはもちろん経験はなく、 開発には足掛け3年を要した。できあがった試験機は分解して運ばれたが、 100トンの台座、長さ22メートルの柱など巨大な部品を、ベッドタウンを抜けて輸送するのは至難の技だった。 3日間もかけておごそかに運ばれたという。
「この装置の製造ができることも貴重ですが、 今の日本の交通・住宅事情では、当時と同じように運搬することは不可能でしょう。 そういう意味でもこれほどの装置は大変貴重な存在となっています」
35年の月日を感じさせないほど美しく管理された同センターをまとめる菊池靖彦技手はこう語る。

装置の巨大な心臓部。35年もの年月をまったく感じさせないほど美しい。
あと20年は稼働させたい
設計・建設時以外にも、部材の経年劣化がどれくらい進んでいるかを見極めるために、 大型構造物試験機が用いられることもある。近年のIT技術の進歩によって、 コンピュータ上で精細なシミュレーションが可能になったとはいえ、 実物を用いた大型構造物試験が必要なくなるということはない。むしろ、
「建築物はますます高層化、大空間化が進んでおり、そのぶん部材の強度も増している。 強い力、大きなサイズが測れる試験機のニーズは、さらに高まっています」(中西教授)という。
それだけに、同大では維持管理に力を入れている。メンテナンスを担当するのは島津試験機サービス。 担当の伊東健一は、「大事に使われているお客様のために、あと20年は稼働させたい」と意気込む。
「導入から35年たち、本来なら寿命と言われても仕方のない年。にもかかわらずここまで大きな故障もなく、 徹底した安全管理も図られて、いつでも正しく計測できている。驚くべきことです」(安達教授)
「法令にそった検定では、許容値±1%を上回る±0.5%。 その精度の高さが信頼ある試験結果となり、社会に還元されています」(菊池技手)
後に作られた大型試験機の多くがすでに引退している。だが、同大の試験機の定年は、もうしばらく伸びそうだ。

日本大学理工学部海洋建築工学科 教授
安達 洋 (写真中央)
日本大学理工学部海洋建築工学科 教授
中西 三和 (写真右)
日本大学理工学部大型構造物試験センター 技手
菊池 靖彦 (写真左)