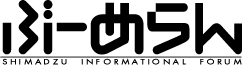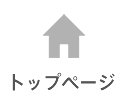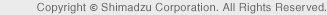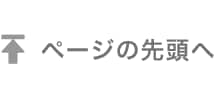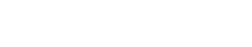 Backnumber
Backnumber
(注)所属・役職および研究・開発、装置などは取材当時のものです。
産学連携が生む最先端テクノロジー7
1ミリのガンを見つける
京都大学大学院工学研究科 材料化学専攻教授 工学博士 木村 俊作
わずか1ミリのごく初期のガンを見つけることができないか。
いま産学は力を合わせ、この壮大なテーマ「分子イメージング技術」の確立に立ち向かっている。
その道筋を大きく進めると期待されるナノ素材を開発したある研究者の「生命を巡る冒険」を追った。
分子イメージング技術の鍵を握る部品
ハンドボールほどの大きさの球体の模型。断面は二層でできていて、中心部にぽっかりと空洞があいている。
「さすが35億年の歴史があるだけに、やはりタンパク質は構造物として一日の長があります」
と球体模型を見据えて語るのは、京都大学大学院工学研究科の木村俊作教授。
この球体の正体は木村教授が開発したナノ粒子。わずか1ミリの微小なガン細胞の姿を捉えるとして期待されている分子イメージング技術に必須の部品で、実際の大きさは直径100ナノメートルほどだ。
分子イメージングでは、分子プローブ(生体分子やナノ粒子などに光を発するフォトン素材などをくっつけたもの)を体内に注射し、それがガンに集まったところでPETなどで全身をスキャニングする。現在の技術では5ミリ程度が限界だが、2ミリあるいは1ミリのごく初期のガンを見つけることを目標に多くの科学者が連携し、研究を重ねている。

自身が開発した生体由来のナノキャリアの模型の前で
注文の多いナノ粒子
ナノ粒子は、いってみればガン細胞に向けて血管の中を走っていくトラックのようなものだ。荷台には、ガンの好物である糖や、フォトン素材を載せられる。特殊な用途に使われるだけに、いくつかの条件がある。
まず、微小血管内でも走れるよう、十分に小さくなくてはならない。また、人体に入るのだから、当然無害である必要がある。人体に入り込んできた侵入者として白血球に食べられてしまったり、腎臓でろ過されてしまったら元も子もない。そして、フォトン素材や場合によっては抗がん剤を自由に載せられ、しかもガンの場所までたどり着いたらそれを降ろしてくれなければならない。
小さいけれど頑丈で、人に優しくしかも融通が利くという極めて難しい要件を満たさなければならないのだ。
これまで、ナノ粒子には主に合成高分子が使われてきた。石油などに由来する合成高分子は、さまざまな条件をクリアして臨床で使われてはいるが、「本当に副作用はないのか」と突き詰めると疑問も残る。
生体由来のリポソームを使う方法もある。異物と認識されないよう、表面に特殊素材をコートすること、まるでステルス戦闘機のように、血管のなかを移動するステルスリポソームというナノ粒子がつくれる。だが、そのコート材にまったく毒性がないかといわれると、それも不確かだ。また、脂で構成されるリポソームのなかに薬剤やフォトン素材を封入してしまうと、肝心の場面で十分に溶け出してこないという恐れもある。

木村俊作教授(左)と島津製作所小関英一主幹研究員(右)
理想的な素材が見つかった
木村教授は、細菌から取りだしたペプチド(アミノ酸)を使ったカプセル「ペプトソーム」を開発。それをナノキャリアとして応用できないかと研究している。「アミノ酸を使った複合体だから、タンパク質と基本的には同じ。生体にはやさしいのです。また、ペプチドは機能性を持つ分子として非常に洗練された構造を持っており、かなり自由に機能を追加することができる。人間のつかっている20種のアミノ酸は分解されやすいのですが、細菌が使っているもののいくつかは、非常に構造がしっかりしていて、運んでいる途中で分解されることもない。理想的な素材じゃないかと思います」
ペプチドには、水になじむ性質のものと水をはじく性質のものが二種類ある。性質の異なるペプチドを表裏重ね合わせ、水なり脂なりに浸けると、くるりと丸くなり球体を形作る。
球体の内側の空間に飛び出しているバネは、薬剤を載せる役目を果たす。バネに使う分子を選べば、
pHの変化や超音波を当てることで、バネを壊して載せている薬剤を放り出す仕組みもつくることもできる。
要件はほぼ満たされた。
「中学生時代はラジオ少年だった」という木村教授。いつかは分子でトランジスタを作りたいという夢を持ち、高分子材料の研究を重ねてきた。工学部の枠にはまらず、生化学にも積極的に進出し、ペプチドの構造や生成の仕組みの解明に取り組んできた。ペプトソームもその過程でできたもので、分子イメージングの研究が学術界にひとつの潮流をつくっていくのを見て、これを利用できないかと参加したという。

100±20ナノの精度を
今後の当面の課題は、カプセルの大きさを直径100ナノメートル(1万分の1ミリ)にそろえることだ。ガン細胞は急速に成長するため、周辺の組織がしっかりしていない。そのため、直径100ナノメートル程度のものは、組織のすき間をどんどん漏れ出していく。組織がしっかりしている正常組織の周辺は素通りしていくので、ガン組織のところのカプセルの濃度はどんどん高まるという仕組みだ。
だが、100ナノを狙っていても1割程度は150ナノのものが、さらに数パーセントは200ナノのものができてしまう。これを100±20ナノメートル以内に収めるのが目標だ。
「ナノ粒子が形成される時の機構を突き詰めていけば、達成できるかもしれません。でもそれが難しければ、ふるいにかけて集めるという方法もあると考えています」(島津製作所 基盤技術研究所 小関英一主幹研究員)
木村教授と小関は、京都大学大学院の先輩後輩にあたる。当時助手として木村教授が展開していた研究の一つを、小関は院生として協同して遂行していた。その後、小関は島津に入社し、分子イメージング技術の確立に力を入れる木村教授との共同研究を担当した。20年ぶりのチーム再結成だ。
「なぜ生体系が自身の構造にアミノ酸を選んだか、ぼくらはまだよくわからないんです。でも天然のものがそれを使っているのには何か理由があるはず。いつかそれを明らかにしたい」(木村教授)
分子イメージング技術開発の延長線上には、もしかしたら生命の秘密が隠されているかもしれない。

京都大学大学院工学研究科
材料化学専攻教授 工学博士
木村 俊作(きむら しゅんさく)
1976年京都大学工学部卒、1982年同工学研究科終了。同大講師、助教授を経て、1999年教授に就任。同年、高分子学会賞を受賞。有機化合物をベースにした生体関連高分子の精密合成や分子組織化を専門とし、生命現象の解明や近未来の情報社会を担うデバイスの開発を目指している。
(注)所属・役職および研究・開発、装置などは取材当時のものです。