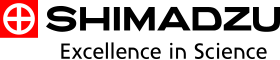数万人に1人のサインを見逃さないために
グループ3社が挑んだ「命を守る検査」
検査技師が慎重に取り扱うのは、生後5日前後の赤ちゃんから採取した「血液ろ紙(乾燥血液スポット:DBS)」。小さな踵から採取した一滴の血が乾いた跡から、わずかな数値の違いを読み取る検査が始まります。新生児の命に直結する、緊張感のある時間が流れます。


新生児マススクリーニングとは
日本では、原則として全ての新生児が、公費で20種類の疾患の「新生児マススクリーニング」を受けています。これは、先天性代謝異常症などの生まれつきの病気を早期に見つけ、適切な治療につなげるための仕組みです。スクリーニングの名の通り「ふるい分け検査」であり、陽性疑いの結果が出た場合は、二次検査・診断を経て治療へと進みます。
希少疾患の早期発見を目指す新しい検査
「『拡大』新生児マススクリーニング」
研究の進歩により、これまで治療が難しかった病気にも、新たな治療法が生まれています。
重症複合免疫不全症(SCID)、脊髄性筋萎縮症(SMA)、ライソゾーム病は希少疾患ですが、造血幹細胞移植、遺伝子治療、核酸医薬品などの技術によって、現在では治療が可能となっています。これらの疾患を早期に発見するための取り組みが、「『拡大』新生児マススクリーニング」です。
現時点では、「『拡大』新生児マススクリーニング」は、従来の「新生児マススクリーニング」のように、日本全国のすべての新生児が公費で受けられる検査になっていません。しかしこのうちSCIDとSMAについては、将来的に公費スクリーニングに追加するための検証と全国展開に向けた体制整備のため、政府が主導して、希望する自治体が参加を申し出る形で試験的な取り組み(実証事業)が行われています。
京都府と京都市は、2025年4月からこの実証事業に参加し、すべての新生児に「SCIDとSMAを対象とした新生児マススクリーニング」を提供できるよう、体制を整えました。

『一気通貫プロジェクト』実現に向けて3社が連携
島津グループは、「装置」「試薬」「検査運用」の3領域で連携し、「新生児マススクリーニング」と「『拡大』新生児マススクリーニング」に取り組んでいます。
島津製作所は、新生児マススクリーニングに対応する分析装置である、「高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS)」を提供してきました。さらに、コロナ禍では全自動PCR装置「AutoAmp」や新型コロナウイルス用PCR試薬を開発・販売し、検査現場の効率化に貢献しています。

島津製作所のメンバー
島津ダイアグノスティクスは、「『拡大』新生児マススクリーニング」向けのPCR試薬キット「TKSneoFinder」を開発しました 。

島津ダイアグノスティクスのメンバー
島津テクノリサーチは、コロナ禍で培ったPCR検査技術の運用ノウハウと、衛生検査所としての高品質な衛生検査体制を有しています。

島津テクノリサーチのメンバー
試薬開発の課題を克服!原因分析で導いた答え
島津ダイアグノスティクスの試薬開発メンバーが当時を振り返ります。
「試薬をテスト評価いただいた現場からは、多くのニーズや改善要望が寄せられました。
『数万~数十万人に1人という疾患に対して、偽陽性(病気ではないのに陽性と判断)が多すぎる』『数値にばらつきがある』などの指摘が続出。改良を試みたところ、かえって状況が悪化することもありました。どうすればよいか、途方に暮れたときもあった——」
そこで、原因の特定と改善のために一度冷静になって原因を深掘り。試薬を製造する際に使用する原材料の品質向上や出荷時の品質検査を改善することで、安定した試薬を提供できるようになりました。


衛生検査所を整備し新規参入へ
「『拡大』新生児マススクリーニング」に参入するには、すでに公費で行われている20疾患の新生児マススクリーニングに対応できることに加え、自治体が設定した要件 を満たす必要がありました。数万に1人を見逃さないために設定された要件は非常に高いものでした 。

島津テクノリサーチは、コロナ禍での検査運用で培ったPCR検査のノウハウの活用や衛生検査所登録を行うなどして、京都府・市が設定した要件を満たし、新生児マススクリーニング分野に新規参入を果たしました。

担当者が当時を回想して話をしてくれました。
――京都府から新生児マススクリーニング検査の委託を受けるにあたり、必要な施設や機器、手順書、検査担当者の技術、さらに検査品質を保証するための精度管理データを整備しました。しかし、実際に検査を開始するには、それだけでは不十分でした。
新生児マススクリーニングでは、ろ紙血(新生児の血液をろ紙に染み込ませたもの)が検体として使用され、郵送で検査施設に届けられます。この検査では施設ごとに異なる試薬や機器を使用するため、全国共通の基準値がなく、各施設が独自に「カットオフ値」(判定基準)を設定する必要があります。
そこで京都府の協力を得て、過去に採取された新生児のろ紙血検体を使用し、1か月間で1,787検体を測定・解析しました。この結果、当施設において適切なカットオフ値を設定することができ、最終的に検査体制を確立しました。
こうした一連の準備を通じて改めて実感したのは、「『赤ちゃんの一生がかかっている検査』に関わるための厳格な信頼の積み上げが不可欠だということでした。」――

数多くの検体の中から、何万人に1人というサインを見逃さず、必要な医療につなげる「命を守るサイクル」に携わる責任を胸に、運用を続ける。その想いをもって、島津テクノリサーチは京都府の公費検査を担当し、地域のみなさまの信頼に応える体制を構築しています。今後も、現場で得られた改善知見を装置や試薬に還元し、検査の精度と安定性をさらに高められるよう3社のシナジーを高めてまいります。
3社が自社の強みを生かして「命を守る検査」を実現した取り組みは、社是や経営理念の実践に向けて、夢や想いを持って主体的に行動するチームの活動として高く評価されました。その結果社内表彰「First a Dream賞」に選出されました。
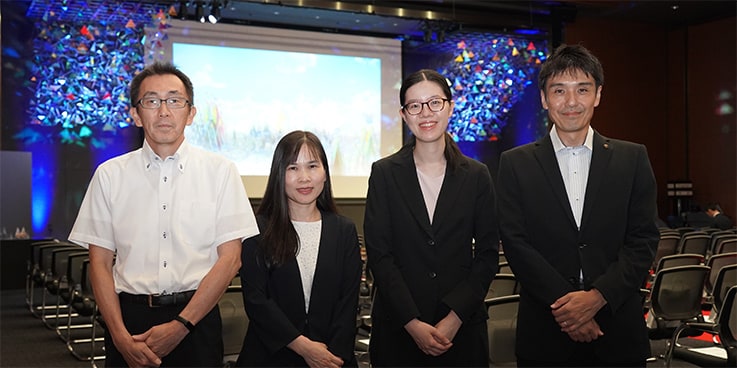
「First a Dream賞」授賞式に参加したメンバー
担当者のコメント
試薬開発から検査までを一気通貫でご提供できるのは、島津グループならではの強みです。島津テクノリサーチの検査現場では、毎日新生児の命を預かる検査を行っています。ここで得られた知見や改良点を島津製作所は確実に装置・解析へ反映し、PCR試薬の改善要望を島津ダイアグノスティクスが形にする。そうして得られたノウハウを注ぎ込んだ製品や試薬で、世界の新生児医療に貢献したいと考えています。
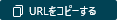 タイトルとURLをコピーしました
タイトルとURLをコピーしました