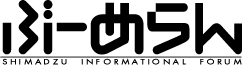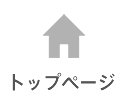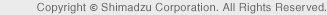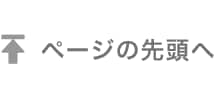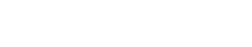 Backnumber
Backnumber

魚の国に生まれて
株式会社ウエカツ水産代表取締役 上田 勝彦
元漁師で元官僚。全国を飛び回り、包丁を振るう。
無私の情熱が目指すのは、衰退する魚食文化の復興だ。
サカナを伝える
沖縄の水産高校生と牡蠣の養殖事業を立ち上げつつある傍ら、北海道の生協からの依頼で主婦向けの調理講習をする。次の日は山陰の漁協で漁師たちを相手に活締めの技術を指導する。株式会社ウエカツ水産代表の上田勝彦氏のスケジュール帳は、数ヶ月先まで真っ黒だ。
一言でいえば、魚食文化の伝道師。名刺には、「漁業・魚食の事、よろず相談承ります」と刷り込まれている。生産、流通、消費のすべての段階で、サカナの消費を絶やさぬための取り組みに知恵を絞り、汗を流すのが仕事だ。呼ばれれば、どこへでも行く。

危機に瀕する魚食文化
アジアの東の端に位置し、四方を海に囲まれた日本。有史以前から主なタンパク源は魚だった。魚を食べる習慣は多彩な調理法や保存法を生み、やがて「魚食文化」に成長した。
ところが数千年にわたって受け継がれてきた魚食が、ここ数年で消滅の危機に瀕しているという。厚生労働省の調査によれば、家庭での魚類と肉類の消費量は、長きにわたり魚類のほうが多かったが、2006年から2009年の間に逆転した。
「畜産業界は、近年非常にがんばった。対して水産業界は過去の繁栄の上にあぐらをかいてしまった。その違いがこの結果につながったのではないか」と上田氏は指摘する。
「魚調理には大きなハードルがあると言われています」と上田氏は続ける。臭みがある、ゴミが出る、料理に手間がかかる、骨がある、調理のレパートリーが限られる、肉に比べて割高の6つ、いわば“六重苦”だ。これが消費者が店頭で魚を手に取る機会を減らしていると見る。
「よく調べてみると、この結果は必ずしも事実と一致しないことがわかる。ほとんどは先入観によるもので、ちょっとしたコツを知っていれば、どれも解決できることばかりです。大切なのは、困っていることはなんなのか、それをよく聞いて理解して、目の前で答えを出してあげること。我々が何をなすべきかは明確なんです」
かつて、多世代が一つの家に同居しているのが当たり前だった時代、魚のさばき方、調理法は台所で実践的に伝えられていった。しかし、核家族化が進み世代の断絶が起こった。おいしくて安い旬の魚を教えてくれ、魚の下ごしらえをしてくれていた小売店舗、いわゆる魚屋さんも、いまや町から姿を消しつつある。効率を求める流通業界の波に呑まれてしまったのだ。加えて、専業主婦が減って、家事に当てられる時間が減ったことも少なからず影響しているだろう。魚の栄養価が高いことは知っていても、手間なくおいしく作れるというイメージから、肉のパックを手に取ることが多いという。
「生産・流通の現場には、良いものを売っていれば消費者はついてくるだろうという慢心があった。しかし、家庭で毎日高級魚を食べるはずがないし、家庭の食卓は魚だけで作られているわけでもない。魚を売ろうと思えば、消費者に寄り添って、日々の食卓を提案しなければならないのです」
漁業の現場に飛び込む
上田氏は昨年まで水産庁のキャリア官僚だった。長崎大学水産学部の3年生のときに、長崎市の西に位置する野母半島でシイラ漁の漁師に弟子入り。半漁半学生活を送った。そのまま漁師になろうかとも考えていたが、当時から漁村の高齢化と人材不足は深刻で、漁師らの現場の声を中央に伝えなければと公務員試験を受けた。
水産庁職員としての彼の働き方は異質だった。例えば、本来であれば、資源を管理する立場であり、決められたルールの下に、漁業の適正と資源状態について調査し、確認するのが役人の仕事。だが、上田氏は時には共に漁をし、水揚げや販売に加わり、漁師や魚屋、飲食店や消費者の声にも耳を傾けた。
「現場は真剣に仕事をしている。でも、衰退の兆しは明らかで、だれかが支えなければ漁師は廃業を余儀なくされる。では支えるのはだれか。国でもなければ自治体でもない。消費なんです。獲ったものを運んで、調理して、食べる。その流れが現場を支え、国の力となり、魚食文化をつないでいくのです」
そう気付いた上田氏は、本来の仕事に加え、食育や調理などの講習を積極的に引き受け、全国を飛び回るようになった。
魚を知り尽くした上田氏の講習は、巷の料理教室とは一味も二味も違う。旬の魚がおいしくなる理由、今この味が生まれるのはなぜなのかを、魚の生態や漁獲法から解説する。調理法もレシピを紹介するのではなく、“仕組み”だと言う。塩を打つことや焼くことによる肉質の変化や調味の効果を実演しながら教えていく。
「レシピは暗記。だから学んでも家庭での再現性が低い。料理の仕組みをわかりやすく伝え、それを理解して納得すれば、家に帰っても応用できて、家庭の魚料理の幅が広がるんです」
においの出ないゴミの捨て方や、魚の生臭さの上手な取り方、まな板の洗い方なども盛り込み、台所の悩みに丁寧に応えていく。講習を受けた人は、そこで魚のおいしさと料理の簡便さに目覚め、その感動をさらに次の人たちに伝えていくという循環も生まれ始めている。
天命を知って
2015年、上田氏は、50歳にして24年勤めた水産庁を辞した。役人時代から関わってきた魚食文化の復興を、本業に据えるためだ。
「漁業を支えるために自分にできることは何かと考えたら、他に道はなかった。とはいえエネルギーを相当使う仕事でもあるので、体力、精神力のあるうちにと考えると、定年を待っていては無理だったというわけです」と笑う。
民間人となった今でも、上田氏の言から「日本」「この国」という言葉が消えることはない。
「本来、政策とは哲学から生まれるものです。特に食料政策におけるその哲学とは、自然界の仕組みの上に成り立って決して曲げられないもの。日本の地勢と気候を踏まえて、この地に住む人間が未来も自立して食べていける環境を整えようとすれば、「魚、米、野菜、時々肉」という、我が国の風土に根差した食のかたちを再構築するしかない。それが国家の役割だと思う」と上田氏は自らの“政策”を語る。
たった一人。だがその言葉は会った人の心を確実に動かしていく。停滞する業界の“触媒”として、大きなうねりを起こそうとしている。

上田 勝彦(うえだ かつひこ)
株式会社ウエカツ水産代表取締役。東京海洋大学客員教授。1964年島根県生まれ。長崎大学水産学部在学中に漁師として活動。91年水産庁入庁。瀬戸内海漁業調整事務所、遠洋課捕鯨班、資源開発センター、資源管理課などで公務に従事。2015年退職。「サカナ伝えて、国興す」を社是に、日本の食卓と漁業の生産現場をつなぎなおす活動を展開している。近著に『旬を楽しむ魚の教科書』(宝島社)、『ウエカツの目からウロコの魚料理』(東京書籍)などがある。