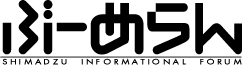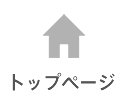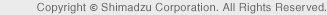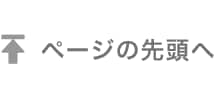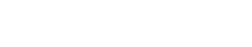 Backnumber
Backnumber

Special Edition “respect”
「自分を尊ぶ努力。」
増田 明美

10代にして彗星のごとく登場し、
日本の女子マラソン界で一時代を築き上げた増田明美さん。
引退後、スポーツジャーナリストや解説者、ラジオのパーソナリティ、
ドラマ出演など、マルチな分野で活躍している。
今も障がい者スポーツの取材や海外NGO活動に取り組むなど、
新分野に挑み続けている増田さんの軌跡を追いかける。
スポーツは苦手だった
28歳で引退するまで、マラソンを中心とする陸上競技に没頭してきましたが、ランナーとしてスタートラインに立ったのは決して早くはありませんでした。陸上部に所属したのは中学の途中からで、本格的なトレーニングを開始したのは高校に進学してから。それ以前は長い距離を走る能力があることにも気づかないばかりか、運動神経は無い方なのだと思い込んでいました。
実際、体育の授業では短距離走が苦手でしたし、跳び箱や球技もうまくできませんでした。スポーツよりも興味を抱いていたのは作文や音楽。小6の時に読んだ『二十四の瞳』に憧れ、将来は学校の先生になろうと夢見ていました。
中学校では軟式テニス部に入ったものの芽が出ずじまい。ただ、なぜか長距離を走るトレーニングだけはいつもトップで、男の子よりも速かったんです。実家が農家で、幼い頃から鬼ごっこでみかん山を走り回り、小学校まで2.5キロの道を往復し、中学校でも30分以上かけて自転車で通っていたことから、知らず知らずのうちに足腰が鍛えられていたのでしょう。
そんな私を見ていた陸上部の先生に、町内の駅伝大会に出ないかと誘われたことが、私の運命を大きく変えることとなりました。初めて走ったその駅伝で、高校生の男子を追い抜くほどの好成績を収めたのをきっかけに陸上部に転部。1年後の800m走で千葉県新記録を出しました。良い結果が出ると、自然と頑張る気持ちが芽生えるもので、3年生の時には全国4位に入賞するまでに成長していました。
自分に自信が持てるようになるって、こういうことなんだ―。陸上の成績がどんどん上がっていく自分を見て、そんな感覚が芽生えました。
それまでの私は、頑張ったことに満足していても、いつも理想と現実には大きな差があったのです。しかし、陸上では頑張れば頑張るほど自信がつき、良い結果がついてくる。これで楽しくないわけはありません。陸上競技が自分自身を肯定する心や、前に向かう自尊感情を育んでくれました。
五輪で勝たなければ何も得られない
進学した成田高校は陸上競技の名門で、仲間はそれぞれの競技で全国3番以内というハイレベル。監督の家に一緒に下宿していた同じ800mの選手に負けまいと、隠れて過酷な自主練をする毎日は、絶対に戻りたくない大変な日々でした。でも、本当のライバルを知ることができましたし、高い目標を持つ仲間との日々で実力はめきめきと上がり、トラック競技やロード競技に出場するたびに、高校記録はもちろん、日本記録も次々と塗り替えていきました。18歳で初めて出場したフルマラソンでは日本記録をいきなり更新。“天才少女”と呼んでくださるメディアもありましたね。
初マラソンから2年後のロサンゼルスオリンピックでは、女子マラソンが正式に競技化されることが決まっていました。当初、夢だった教員を目指して大学に進学するつもりでしたが、オリンピックという目標に専念するため、環境の整った社会人チームに進みました。そして、2年間、覚悟を決めて練習に励んでいきました。
にもかかわらず、ロサンゼルスでは16キロ地点で途中棄権。いつも先行逃げ切り型のレースをする私は、あの日も最初からトップを走っていました。しかし、ハードな練習ですでに疲労をためていたことで、あえなく集団に飲み込まれてしまうと、弱気な自分が表に出てしまいました。いつの間にか足が止まっていたんです。
スイスのアンデルセン選手がフラフラになりながらも最後まで完走した有名なシーンは、実は同じレースでした。それだけに私に対する風当たりは相当なものでした。どれだけ新記録を出し、どんなに天才少女と持てはやされても、その人の評価はオリンピックの結果がすべてなんです。ましてや途中棄権なんて。当時は事実を受け入れられず、他の理由を必死に探している自分がいましたが、非常に厳しい現実を思い知らされました。

引退してからが人生
ロサンゼルスオリンピック後も休息期間をはさみながら、現役生活を続けました。オリンピックの大舞台から4年ぶりに走った大阪国際女子マラソンでは、自己ワースト記録ではありましたが、なんとか完走。途中棄権した自分はそこで吹っ切ったつもりでした。
けれども、実際は過去を引きずり続けていたんです。引退後もことあるたびにあのシーンを思い出している自分がいました。有森裕子さんや高橋尚子さんらがオリンピックでメダルを獲得しましたが、その姿を間近に見て祝福しながらも、心のどこかで「オリンピックが無ければ人生が違っていたはず」と過去の自分と比較してしまっていました。
あの失敗は人生の一コマに過ぎないと冷静に考えられるようになったのは、20年以上経ってからのこと。2005年に結婚して心が安定するとともに、引退後の仕事が軌道に乗ったのが契機になったのだと思います。
引退後は本当に様々なことにチャレンジしてきましたね。マラソンにかかわる仕事はもちろんのこと、ドラマに主演したこともいい経験でした。また、声がいいと評価されてラジオのパーソナリティにも挑戦しましたし、テレビで都はるみさんのモノマネをしたこともありました。どこかに過去の嫌な自分を振り切りたいという気持ちがあったのかもしれませんね。
その中でも一貫して力を入れてきたのが、スポーツジャーナリストとしての仕事です。この分野にチャレンジしようと思ったきっかけは、ラストランで足の痛みがひどくなって途中棄権したことです。レース後の診察で、疲労骨折が何箇所も見つかりました。原因は成長期の減量です。若い頃は“太ると速く走れなくなる”と思い込み、極度に減量しながらハードなトレーニングを続けていたんです。その結果、2年間にわたって生理が止まった時期があり、エストロゲンの分泌も止まって骨がもろくなっていました。代表となったこと、そこで結果を出せなかったことによるストレスも災いしたのでしょう。私の体は本当にボロボロでした。
当時、選手の中には私のように減量している人も少なくありませんでした。成長期の女性アスリートの体の問題に警鐘を鳴らしたいとの思いが、私をスポーツジャーナリストとしての道に駆り立てました。小学校の頃、担任の片岡先生がおっしゃってくださった「将来、増田さんは書く人になるのかもね」という、心に残っていた言葉も、背中を押してくれました。
選手の強さの源を伝える
マラソンは、走る人の人間性が色濃く表現されるスポーツです。42.195キロの長い距離を走る約2時間数十分間、選手は自分と向き合い続けるほかありません。だからこそ、レースでは強い自分も、弱い自分もすべてがさらけ出されてしまうのです。最初から先頭を走ることでモチベーションを保つ私のような人や、反対に後半から追い上げていく選手もいますし、駆け引きや競り合いに長けているなど、選手たちは非常に個性豊かです。
その選手がなぜ強いのかは、選手の人となりを知ればより具体的に理解できるものです。だから、私は解説者として趣味や家族、プライベートでの素顔など、強さを引き出すその人らしさまで細かく伝えていくスタイルを取っています。
このスタイルには、何よりも取材が大切です。重要なのは、取材には一人で現地に行くこと。テレビカメラなどのクルーがいると、選手はそれだけでエネルギーを取られてしまって真の姿が見えにくくなるのです。なので必ず増田明美としてアポを取り、自分で行きます。
私の取材スタイルは、先日他界された永六輔さんの影響を大きく受けています。永さんはいつも風景が立体的になるようなお話をされる方。「永さんのように、においを伝えられるようになりたい」と率直にお伝えしたところ、「取材とは“材を取る”ことですよ。気になる人がいたら現地に出向いてください」とアドバイスをして頂きました。
確かに資料から起こすだけの原稿と、本人と会ってその人を感じて書くのでは明らかに質が異なります。それからは“材を取る”ことを肝に銘じて、選手たちの素顔や生の声を多くの人たちに伝えることで、よりレースが深く、面白くなるような記事づくりや解説をしようと努力してきました。
「あなたが“万が一”結婚する時には仲人をしますよ」と永さんは冗談半分で約束してくださいました。私の結婚が決まった時、奥様がご逝去されていたので司会をしてくださることになっていたのですが、結婚式の司会をするのは初めてだったそうです。永さんは一瞬“キャンドルサービス”という言葉を忘れてしまい、その代わりに“おロウソクの点火式です”と。会場は大爆笑でした。

東京オリンピックのその先へ
2020年の東京オリンピック・パラリンピックは、日本にとって大きなチャンスになります。多くの海外の方が来日され、異なる文化や言葉に触れる機会が増えるので、おもてなしのために国際理解を深めることが大切でしょう。また、パラリンピックが行われることは、スロープなどのハード面だけでなく、心のバリアフリー化を進める絶好の機会になると思います。真夏の東京の酷暑が取りざたされていますが、気温の上げ幅を抑えるような街づくりが実現できれば、市民の生活そのものを快適にできます。今、1964年の東京オリンピックのことを嬉しそうに話してくれる人がたくさんいます。「2020年のオリンピック・パラリンピックで…」と50年後に熱く語ってくれる人も増えることでしょう。
これを機会にスポーツの持つ様々な力を将来につなげていけたらいいですね。スポーツには医療性や教育性、コミュニケーション性などの側面があります。スポーツをすることで心の病を改善する取り組みも行われています。子どもたちがスポーツを通してモラルやルールを体で学び、親と一緒に汗をかくことでコミュニケーションも密になっていくのです。
私も現役時代から知的障がい者の人たちと一緒に走っていますが、教えることよりも学ぶことの方が多くあります。視覚障がい者のランナーの伴走でもそうです。競技者として自己中心的だった心に、相手のことを思いやる気持ちが育まれました。
また、国際NGOの活動を通じ、発展途上国の女の子を支援しています。一昨年、視察に行った西アフリカのトーゴで、スポーツを通して自尊感情が高まっていく姿を目の当たりにしました。貧しい内陸部の地域では、女の子は教育も受けられずに農作業に従事し、10代で嫁がされています。ところが村ごとに女子サッカーチームをつくったところ、以前は強い男性社会に隠れて消極的だった女の子たちから、将来、「国のリーダーを目指したい」「ジャーナリストになりたい」という声が上がってくるようになったのです。その姿を村の男性たちも応援してくれています。
スポーツの持つ力を信じて、これからもどんどん活動を広げていきたいと思います。(談)

増田 明美(ますだ あけみ)
1964年、千葉県生まれ。成田高校在学中に陸上競技の長距離種目で次々に日本記録を樹立し注目を浴びる。1982年に初マラソンで日本新記録を達成。1984年のロサンゼルスオリンピック出場を果たす。1992 年に引退するまでの13年間で、日本最高記録は12回、世界最高記録は2回更新している。引退後はスポーツライターやマラソン解説者、ラジオパーソナリティなど多岐にわたる舞台で活躍中。