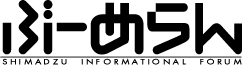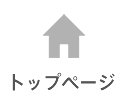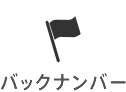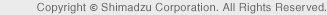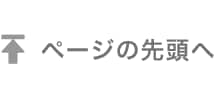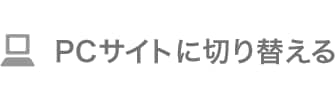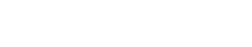 Backnumber
Backnumber
挑戦の系譜
クロマトグラフ第3の波
世界最大の分析機器展示会Pittcon 2015 Conference&Expoで、Pittcon Editors' Awardsの最高賞を獲得した島津製作所のNexera UC。
超臨界流体を活用したこの装置は、分析のスタンダードを変える可能性を秘めている。その開発の舞台裏を追った。
息を飲む分析スピード
「これがSFCか。すごいですね」
2014年春、翌年に発売を控えていた超臨界流体クロマトグラフ(SFC)のアプリケーションの開発担当者はディスプレイに釘付けになった。
「まったくだ」
開発の責任者で、作業を見守っていた島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス事業統括部 LCビジネスユニット長の冨田眞巳自身、試作機が高速でたたき出すデータに目を見張るばかりだった。
クロマトグラフィーは物質内に含まれる様々な成分を分離させることで、それが何なのかを分析する手法だ。ガスクロマトグラフ(GC)は1950年頃から、液体クロマトグラフ(LC)は1970年頃から普及し、様々な分析の現場で、物質の特性や目的、用途に応じて使い分けられてきた。2000年代後半、そこに割って入ってきたのが、高速分析の普及にともなって再注目されている超臨界流体クロマトグラフ(SFC)だ。LCが得意とする液体に溶けやすい成分だけでなく、GCに向いた気化しやすい成分まで幅広く測定できる。
これに一番反応したのは製薬業界だ。SFCは、組成はまったく同じだが、構造の違う光学異性体※1など、従来のクロマトグラフでは分離に難のあった物質をもきれいに分離できる。1960年代に社会問題となった催奇性による薬害は、この光学異性体が薬剤に含まれており、一方が強い毒性を持っていたために引き起こされたものだった。現在では必ず毒性のある方を分離して回収しなければならないが、LCでは分離に時間がかかるため、新たな手法が待たれていた。他にも光学異性体を持つ薬品原料は多く、SFCでないと分離が難しい薬剤も少なくない。
※1…光学異性体 同じ組成でも立体構造が右手と左手の関係のように、鏡に映したような2つの形を持つ物質で、化学的物性がほぼ等しいため分離が困難である場合が多い。一方の異性体を選択的に合成する有用な方法を開発したことで2001年に野依良治教授がノーベル化学賞を受賞。

超臨界流体の活用で分析の常識を根本から変えると期待されているNexera UC。
不意に舞い込んだ依頼
2011年の春。LCビジネスユニット装置開発グループ副グループ長の岩田庸助は、島津製作所本社を訪れた大阪大学の馬場健史准教授(当時)からの意外な申し出に戸惑っていた。
「おもしろい技術があるので、それを使って一緒にSFCシステムを開発しましょう」
馬場准教授はSFC研究の第一人者だ。准教授の言うおもしろい技術とは、SFCと超臨界流体抽出(SFE)技術を組み合わせたもの。SFEとは、超臨界流体※2を用いて、固体試料などから直接成分を抽出する技術だ。従来、分析装置にかける前に行う前処理では、職人的な技量や多くの時間が必要なために自動化が困難だったが、この技術ではそこを大幅に簡易化できる。同じ超臨界流体を使うSFCとの相性もよい。この技術は、食品の残留農薬や機能性成分分析に積極的に取り組む宮崎県総合農業試験場の安藤孝部長がすでに実用化していたが、これまでSFEとSFC、そして測定を行う質量分析計(MS)を接続した一連(オンライン)の分析システムはなかった。オンラインにできれば、装置間を移動させる間に試料が空気に触れることがなくなり、酸化によって成分の変化が起こってしまうこれまでの前処理法の弱点を補える。馬場准教授としては、ぜひともほしい装置だったのだ。また、微量の血液を用いて疾患マーカの探索を行っている神戸大学医学部の吉田優准教授もこのユニークな特長を活かして研究の加速を狙っていた一人であった。
※2…臨界点(各物質が固有に持つ温度・圧力の点で、臨界点以上では液体と気体の共存状態がなくなる状態に変化する)を超えた状態の流体で、気体の低粘性、高拡散性と、液体の高溶解性という両方の性質を併せ持つ。

LCビジネスユニット 装置開発グループ 岩田庸助 副グループ長
「つまんで離す」
馬場准教授の依頼は、島津としてもSFCに参入する好機だった。
満を持して開発が始まったが、もちろん一筋縄ではいかなかった。一番の問題となったのは、圧力を制御するバルブだ。SFCでは超臨界流体を充填したチャンバーのわずかな圧力変化が分離状態に影響を及ぼす。その圧力を制御するバルブの正確な動作が分離分析の肝だが、バルブ出口では減圧にともなって超臨界流体内に溶けていた試料の成分が、バルブ付近で結晶化し、それが詰まってしまうことで圧力が不安定となる現象が長くSFCの課題となっていた。「実験をしている時間と、トラブル対応の時間が同じくらいだった」と、学生時代に超臨界流体の研究をしていたLCビジネスユニット装置開発グループ副グループ長の舟田康裕は当時の研究を振り返る。
これまで使われていたニードルバルブは、大きな容量が圧力安定の妨げとなり、圧力の変動を生み出していただけでなく、構造上、析出した成分がつまりやすい。そのため容量が小さく、まったく新しい構造のバルブを必要としていた。当初、岩田はバルブを製造する海外メーカーに問い合わせたが、作れると頷いたところは一社もなかった。
「ならば作るか」
岩田は島津製作所の基盤技術研究所へバルブの開発を依頼。入社3年目の後藤洋臣が担当となった。
正確なデータをとり、装置の信頼性を上げるためには、詰まりを起こさず、容量が小さく、圧力を一定化するようなバルブを作らなければならない。このミッションを遂行するため、後藤をはじめとする研究チームが何枚もスケッチを描いた。
「いろいろと考えましたが、やはり実現性の高いボール型がいいと思います。これまでLCの逆止弁として使われている実績もありますし、開発に時間はかからないでしょう」

LCビジネスユニット 装置開発グループ 舟田康裕 副グループ長
何度目かのミーティングの席で後藤は、そう岩田に伝えた。しかし、岩田は意外な回答をした。
「それもいいけど、例のやつはどうなの?完成まで時間がかかってもいいからあれも試してみてよ」
「例のやつ」とは、ダイアフラム型とよばれるバルブ。管をピンチでつまむような構造をしており、圧力をかけている時も、いない時もまったく余分な容量がない。後藤が娘の入院していた病院で目にした点滴チューブの調整ツマミから着想を得たもので、「つまんで離す」というシンプルさは、まさにSFCのバルブとして理想的なものだった。うまくいく保証はないが、成功すれば理想的なまったく新しいバルブ構造が実現できる。
完成の目処が立った2012年の1月、大阪大学に2つのバルブを持ち込みテストを行った。結果、ボール型でも十分に圧力変動は減ったが、ダイアフラム型はそれを上回る性能を見せた。なんと圧力変動が既製品の10分の1になったのだ。
「まさか1年でこんないいものができてくるなんて」と馬場准教授は喜びをあらわにしたという。
バルブの目処が立った後、その成果を裏付けするかのように、SFC開発プロジェクトは日本科学技術振興機構(JST)の先端計測分析技術・機器開発プログラムに採択された。開発は加速していった。2013年には試作初号機が完成、SFEを含めた一連の分析システムの開発を経て2014年には実機に近い試作機が完成。試運転に臨んだ。圧倒的な性能は、開発に携わった者たちをも驚かせたという。

基盤技術研究所 後藤洋臣 主任
分析を簡素化するシステム
2015年1月27日、SFEとSFCを組み合わせた新たな超臨界流体分析システムNexera UCが、JSTと大阪大学、神戸大学、宮崎県、そして島津製作所で共同発表された。従来、LCで残留農薬の分析をしようとすると、前処理に15ステップも要していたが、試料を溶かしやすいSFEならたった4ステップで済む。
「前処理で苦労されているお客様は多く、そのソリューションとしても期待されています。そのため、当社のLCをお使いでないお客様からの引き合いも多くあります。どこも提供できなかったものをお客様にご提供でき、お客様の業務を変えることができるかもしれない。それが、なによりも嬉しいです」(冨田ビジネスユニット長)
分析の常識が、ここから変わるかもしれない。

冨田眞巳 LCビジネスユニット長

株式会社島津製作所
分析計測事業部 ライフサイエンス事業統括部 LCビジネスユニット長(部長)
冨田眞巳【中央左】
株式会社島津製作所
分析計測事業部 ライフサイエンス事業統括部 LCビジネスユニット 装置開発グ
ループ 副グループ長(課長)
岩田庸助【右】
株式会社島津製作所
分析計測事業部 ライフサイエンス事業統括部 LCビジネスユニット 装置開発グループ 副グループ長(課長)
舟田康裕【左】
株式会社島津製作所
基盤技術研究所 新事業開発室 新事業開発グループ 主任
後藤洋臣【中央右】