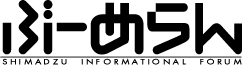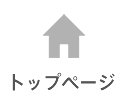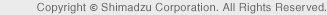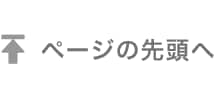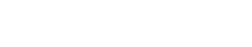 Backnumber
Backnumber

オーロラへ! ― 南極観測隊に欠かせない調理人として
篠原 洋一


2回の越冬を体験した篠原さん。
過酷な場所に赴いた理由は「南極でオーロラを見たいから」。
大きな目標を叶えるべく、奮闘し続けてきた篠原さんに話を伺った。
南極行きを勝ち得るために
オーロラの素晴らしさは、自分の目で見なくてはわからない―南極観測隊の一員だった大学教授から投げかけられた言葉に、見習い調理人だった篠原さんは雷に打たれたような衝撃を受けた。
子どものころから旅と食が大好きだったという篠原さん。18才の当時、地元北海道札幌市の割烹に入り、夢である調理人としての道を歩みはじめたばかりだった。
教授から聞く南極のオーロラは魅力に満ちていた。しかし、料理に携わる身には、あまりに縁遠い世界にも感じられた。
「『偉い人しか行けないんでしょう?』と先生に聞いてみました。すると、研究者ばかりではなく、基地を運営する設営隊に調理担当者もいると教えてくれた上で、『キミにもチャンスがある』と背中を押してくれたんです」
自分の歩んでいる道の先に、南極のオーロラという選択肢がある。会話にしてわずか30分ほどだったが、この短い時間で、篠原さんの運命は劇的に変化した。
教授からは「キャリアを積むこと」「何でも作れるようになること」が大切だと聞いた篠原さんは、以来、寝る間も惜しんで料理の腕を磨き続けた。名店と呼ばれる料亭で働きながら、深夜は居酒屋でアルバイトをした時期もあった。居酒屋なら和洋中あらゆる料理を作る技術が身につくからだ。
「居酒屋で肉じゃがを作るとき、作り方がわからなくなって、手が止まってしまったことがありました。料亭では煮物を作るのは、煮方という天の上の人の仕事。料亭の調理場で働いているのに、何もできない自分がいる。悔しいという気持ちではなく、目から鱗が落ちる思いがしました」
厳しい生活ではあったが、毎日が刺激的で、夢中で走り続けることができた。枕元に南極観測船の“しらせ”とオーロラの写真を貼り、毎朝、「いつか、南極に行くぞ!」と心に誓いながら出かける。強い意志を持って篠原さんは自己研鑽に励んだ。
料理にある程度の自信がついた20代後半、篠原さんは南極観測隊を派遣する国立極地研究所に履歴書を送る。2回連続で選考に落ちてしまうが、篠原さんは諦めずにトライし続け、第33次越冬隊(1991年)の調理担当者に抜擢された。
「小さな“諦めない”の積み重ねが、最終的に大きな結果になることを身に染みて理解しましたね」
教授との会話から、実に10年の月日が流れていた。
美しく恐ろしい自然
南極の地に立ち、篠原さんは憧れ続けたオーロラを眼前にした。その瞬間は生涯、忘れられないという。
「天頂からぐわーっと押し寄せてくるオーロラを見て、鳥肌が立つほど感動しました。しかし、次の刹那、本能的に『怖い』という感情が芽生えたんです。自然は美しいけれども、同時に恐怖も秘めている。確かにこれは実際に見なければわからないと痛感しました」
過酷な自然と向き合う越冬隊員たちをサポートしつつ、篠原さんは南極生活をたっぷりと堪能した。露天風呂を作って酒を飲んだり、ソリで海氷上まで出かけ、おでんを食べながらオーロラ見物をしたり。隊でなければできない貴重な体験だ。
「南極では肉眼で人工衛星が見えることがあるのですが、もの凄い明るい衛星がオーロラの上を横切ったことがありました。翌日、FAXで送られてきた新聞を見る と、スペースシャトルに乗った毛利衛さんが『南極のオーロラは素晴らしかった』とコメントしていました。私たちが見上げていたオーロラを、毛利さんは宇宙から見下ろしていたんですね」
もちろん南極の自然は荒々しい。ブリザードが吹き荒れる日に、上下左右の感覚が無くなる「ホワイトアウト」を経験したこともあった。しかし、憧れに憧れたオーロラがそこにあるから、篠原さんは前を向いて頑張ることができた。

読売新聞 アフロ

脳に食わせる
本業の調理人としても、貴重な経験の連続だったと篠原さんは振り返る。
「旅立つ前、隊長から『調理人は隊の肝心要。士気が上がるも下がるも調理人次第だ』と声をかけられ、身が引き締まる思いがしました」
越冬隊の場合、1年3か月の長きにわたって南極で活動し続ける。零下25度の極寒の地は、ほぼ完全に閉鎖された世界だ。余暇を楽しむ機会はほとんどないからこそ、“食”は数少ない娯楽となるのだ。
「帰国後、何次隊の食はよかったけど、何次隊はダメだったと延々と言われ続けることになるんですよね。だから、必死で料理をする毎日でした」
基地には1年3か月分の食材に加え、予備約300日分がストックされているが、当然、無駄遣いはできない。普段は少ない食材をやりくりした家庭料理的なメニューが中心となる。しかし、数少ない楽しみである食が味気なければ、隊員たちも気が滅入ってしまう。そこで、ときには豪華な食材を使ってごちそうを振る舞った。
「コンセプトは“脳に食わせる”。たとえば、タラバガニと毛ガニをひとりに付き一杯ずつ配って、さらにカニ鍋も作ったりして、カニ尽くしの料理を作ったりしたんですよ」
氷山で流しそうめんをしたり、お弁当を持って遠足に出かけたりといったイベントも開催した。食を通して隊員たちが笑顔になる。まさに隊の要として、明日への英気を養っていた。
帰国後、篠原さんは豪華客船「飛鳥」と「飛鳥II」のシェフとなり、14年間で世界9周約60か国・200都市を巡る。そして、第50次南極地域観測隊(2008年)に加わったあと、現在は横浜のレストラン&バー「Mirai」のオーナーシェフとして、南極などで磨いた腕を振るっている。
「南極を目指したい若者が来店することも少なくありません。世界に飛び立とうとする若い力の背中を押す。それが今の私の使命だと思っています」
店内にはオーロラの写真がズラリと飾られている。自分の目で見なければ、本当の素晴らしさはわからない――かつて自らにかけられたその言葉を、篠原さんは夢見る若者たちに投げかけている。

第33次・第50次 南極地域観測隊調理担当
レストラン&バー「Mirai (みらい)」 オーナーシェフ/p>
篠原洋一 (しのはら よういち)
1962年、北海道生まれ。第33次南極地域観測隊、第50次南極地域観測隊の調理担当者として、南極で越冬をする。豪華客船「飛鳥II」では14年にわたり和食の調理に携わる。現在は多国籍料理と南極メニューを提供するレストラン&バー「Mirai(みらい)」(横浜市中区)のオーナーシェフとして活躍中。