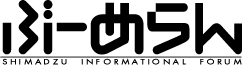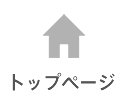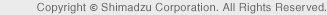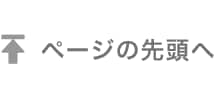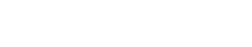 Backnumber
Backnumber

Special Edition “PARADIGM ENJOY”
「描く人」
加藤 久仁生
弱冠31歳にして、日本人初となるアカデミー賞短編アニメーション賞を受賞。
快挙をなしとげた加藤久仁生監督は、悩み、苦しみ、そして存分に楽しみながら、作品を紡ぎ出している。
一枚のスケッチから始まった
アニメーション『つみきのいえ』は、今にも水没しそうな街に建つ一軒の家が舞台だ。一軒ではあるが、実際は10以上の家が、文字通り積み木のように積み上げられてできた建物で、一番上の家だけが、わずかに水面の上に顔を出している。
アカデミー賞短編アニメーション賞を受賞したこの作品は、監督である加藤久仁生さんが描いた一枚のスケッチ画から始まったという。
「ストーリーよりもたいてい最初に一枚の絵が思い浮かぶんです。こんな光景があったらおもしろいな、とか、こんな人がいたらいいな、みたいな」
一言一言確かめるように、とつとつと語る。
幼いころから絵を描くのが好きで、本格的にイラストを学びたいと、美術大学に入学。一枚の絵のなかでの表現を目指していた。だが、3年生のときに受けたアニメーションの授業が転機になった。
「変わった先生で、世界中のいろんな手法で作られたアニメーションを、ただただ流して解説するだけの授業なんです。あとは自分で考えろ、という感じです。そこにあったのは、自分が小さいころから見てきたいわゆるアニメとは違うもので、おもしろかった。ふと、そのとき思ったんです。自分の描いた絵が、動いたらおもしろいかなと」
アニメーションの語源は、ラテン語で霊魂を意味するanima(アニマ)。動かないものに命を与えて動かすという意味だ。
「よく言われることですが、たしかにそんな感じはしましたね。それまで一枚の絵のなかで創り上げていた世界が、時間軸を持って動き始める。そのとき僕の中に全然違う感覚が芽生えたんです」
急速にアニメーションにのめり込んだ美大生は、精力的に作品を制作。在学中に創り上げた作品で、国内の賞も獲得した。
卒業後、株式会社ロボットに就職。CMなどの映像を手がけるとともに、自らの作品作りも進めてきた。
「一枚の絵からスタートして、いろんなラフやコンテを描いてイメージを固めていく作業は、すごく楽しいですね。どういう世界を描こうか。その世界を案内するガイド役は、どういうキャラクターにしていこうか。建物はこんな感じ、小物はこんなイメージ、何度もラフスケッチを描いていくうちに、自分のなかにあるもやもやしたイメージが目に見えてくる。何度やってもおもしろい」


©ROBOT
僕はずっと描いてきた
デジタル技術が普及した現代においても、加藤さんの手がけるアニメーションの基本は「手描き」だ。
原画となるパラパラ漫画を描き、それを影と線に分けて描き直し、一枚一枚パソコンに取り込んでいく。色をつけるなどの作業はパソコンの中で行なうが、仕上がったものは、手描きの風合いが生かされた素朴で味わい深いものばかりだ。
「決してデジタル技術を否定しているわけじゃないんです。デジタル機器がなければ、いまやアニメーションは作れないくらい。でも、自分の描いた絵を動かしたいというのが僕の出発点。原画の部分は、どうしたって手描きなんです」
20代は、「ずっと描いてばかりいた」という。CMや短い作品では、自らの手ですべての原画を描くことも少なくなかった。クライアントなどの意向はあるものの、基本すべてが自分のなかで完結する仕事だ。
だが、『つみきのいえ』を創るにあたって、加藤さんは新たな一歩を踏み出すことになった。エンドロールを入れてもわずか12分の短い作品だが、株式会社ロボットの制作室には、『つみきのいえ』に使用した原画やその他、紙に描いたものがすべて保管されていて、その数は段ボール箱6箱にも及ぶ。当然ながら、それを一人で描き上げるのは不可能だ。携わった人数は、映像部分だけでも15人。その中心に立って、チームを指揮する役割が、加藤さんに課された。


「或る旅人の日記」 2003年 ©ROBOT
言葉にする難しさ
共同で制作していくためには、チームの全員が同じ方を向いていなければならない。作品の世界観を全員が共有して、同じイメージのもと、影をつけたり、色を決めたりするのも、その世界観に従って進めていく。その中心にあるのは、加藤“監督”の言葉だ。
「イメージを共有するのは難しいなと痛感しました。もともとチームプレーが得意なほうじゃないし、描きながらイメージができていくという仕事の仕方をしていたこともあって、初めて顔を合わせる人にうまく伝わらない。自分で絵を描いていけば、こういうことだと伝えられるんだけど、言葉にするのは難しい」
企画で4ヶ月、実作業で6ヶ月。合計10ヶ月間加藤監督とそのチームは、加藤監督の頭のなかにある「もやもや」と格闘。イメージを実現させるために影のタッチをすべて鉛筆で仕上げるなど、随所にこだわりを見せ、その作品の世界が完成した。
温かみのある映像、切なくほろりとさせる老人の人生。リリースされたファンタジーは、世界最大のアニメーションフェスティバル「アヌシー国際アニメーション映画祭」でグランプリを受賞したのをはじめ、内外の約20もの映画賞を受賞。ついにはアカデミー賞短編アニメーション賞獲得と、世界中から絶賛された。
だが、本人はいたって平静だ。
「出来上がったものを観ていると、もっとこうしたかった、もとこうすればよかったというのが次々と湧いてくるんです。観て楽しんでくださっているお客さんがいますから、どこがどうとは言わないのですが」
決して満足はしない。その厳しさこそ、世界をうならせた理由かもしれない。「いつか、心から納得できる作品が作りたい。ただそれだけです」

©ROBOT

『つみきのいえ』 あらすじ
海面が上昇して、徐々に水没していく街。この街に残るただ一人の住人である老人は、水面が上昇するたびに、上へ上へと家を建て増しして難をしのぎながらも、穏やかな毎日を過ごしていた。ある日、老人はお気に入りのパイプを海中へ落してしまう。パイプを拾うためダイビングスーツを着込み、海中に沈む積み重なった家を一つひとつ潜っていくうち、老人は家族とともに暮らした日々を回想する。
DVD「piece of love vol.1 つみきのいえ」発売元:ロボット/販売元:東宝/¥1,995
その日一日の支えになるような映画を
最近になって、自分の目指す方向性が少し見えてきた、という。
「自分のなかに明確なイメージがないと、スタッフを動かすことはできません。同時に、お客さんの心を動かすこともできません。自分のなかに確固としたものを持つこと、そしてそれを表現することが、大事なのかなと」
そのためには、自分の体験に基づいたイメージであることが、何より大切だという。
好きな作品やアーティストは、と尋ねると、スタジオジブリやディズニーの作品にまじって、太宰治や坂口安吾の名前が漏れ出てきた。

©ROBOT
「自分をさらけ出すってことは、気恥ずかしいところもあります。あるけれど、それをやらないといけないなと思うんです。自分が体験したもの、そのとき感じた感情などを起点にして創り上げたものじゃないと、人の心には届かない。仕上がったものが、ドキュメントになるか、ファンタジー(空想)になるかは、料理人の味付け次第ですが、その根っこにあるのが、自分の経験であることが本当に大事なんだと、ようやく気づいたところです」
「アニメーション作品は、決して“役に立つもの”ではありません。だれかの命を救うものでもなければ、生活を便利にするものでもない。でも、何かしら自分の内側から生まれてきたもので、直接的ではなくても、その人が、その日一日生きていく支えになったり、その人の悩みとリンクして、こういうことかって気づきがあるものが創りたいんです」
秋に美術館での展示を予定している。

株式会社ロボット 監督
加藤 久仁生 (かとう くにお)
1977年生まれ。鹿児島県出身。多摩美術大学在学中からアニメーションの自主制作を始める。同大学卒業後、2001年にロボットに入社。アニメーションから絵本まで幅広く創作活動を行っている。主な作品に『或る旅人の日記』、『つみきのいえ』がある。