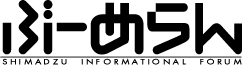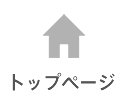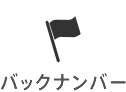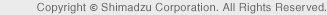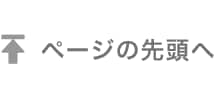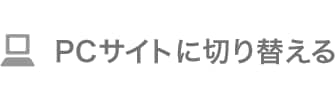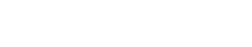 Backnumber
Backnumber

いのちのデザイン
デザインディレクター 川崎 和男
Newsweek誌(日本版)が選出する「世界が尊敬する日本人100人」に2度も選ばれたデザインディレクター川崎和男。日本のデザイン力を世界に知らしめただけでなく、プロダクトデザインそのものの地位を高めた、デザインのパイオニアである。波乱に満ちた半生は、日本の未来のあり方をも示唆している。
ある革新
会議室のドアを開けると、机の上にずらりとキーボードが並べられていた。 PC用キーボードを製造する、ある日本のメーカー。高い技術力で知られていたが、 近年はアジア諸国の圧倒的な価格攻勢に遭い、一時の勢いを失いつつあった。 これでだめなら、もうこの市場から撤退しよう―。 起死回生をかけて招いたのがデザインディレクター川崎和男だった。
アイデアの参考になればと一堂に集めた自社製キーボードを一瞥し、川崎さんはこういった。 「すみません、全部片付けてください。僕が造りたいのはこれです」差し出されたスケッチを目にして、 そこにいただれもが息をのんだ。そこにあったのはキーボードの概念を覆すもの。 だが、だれもが待ち望んでいたものだった。「これを造るには素材開発から始めないといけません。 幸い協力してくれそうな素材メーカーには心あたりがあります」 先ごろ発表され大きな話題となったタッチパネル型のフラットなキーボード。 洗練されたフォルムや未来感あふれるLEDの意匠も見事だが、表面を簡単に拭きとれることで、 雑菌の温床であったり、 飲み物をこぼしただけで使用不能になってしまうといったキーボードの弱点を文字通り払しょくしてしまった。 「デジタル機器には清潔感がない。とくに医療現場などで使われるなら清潔感は欠かせない。 そんなデザインはできないか、ずっと考え続けてきたんです。数学の問題を解くように」

川崎さんがデザインディレクションを行ない、 入力機器のキートップをすべてなくしたフラットデザインが大きな特長の「COOL LEAF」 シリーズキーボード「Φ-QWERTY」。リモコン、電卓もラインアップ。デジタル機器のみならず、 住設機器、医療機器向けの入力装置への展開も期待されている。
絶望を乗り越え
川崎さんは福井県の生まれ。負けず嫌いで幼いころは喧嘩ばかりしていたという。 医学部への進学を考えていたが、大学受験に失敗し浪人していたときに、 イラストレーター横尾忠則(本誌2号登場)の作品に衝撃を受け、美術大学へ進路を変更した。 卒業後、家電メーカーに就職しオーディオのデザインを担当。早くから頭角を現し、 将来を嘱望されたが、28歳のとき交通事故に遭い車いすでの生活を余儀なくされる。
もうデザインはできないかもしれない―失意を抱えて故郷に戻った。だが、ここで大きな出会いがあった。 750年の歴史を誇る「越前打刃物」の職人たちと交流を深め、 工業デザインの思考や方法論を融合した新しいナイフを作りだしたのだ。
木製の柄はいらないと川崎さんが言えば、職人たちは持ちにくいしバランスが悪いと反論。 だが、川崎さんは、持ち手が木製では雑菌が発生しやすいと譲らない。 果たして、できあがったナイフは、持ち手がむき出しの金属でも綿密に重量配分が計算され、 しっくりと手になじんだ。ここで生産されたナイフは、 国内外で数々の賞を受賞し、川崎さんはデザイン界へ復帰を果たす。
以後、川崎さんは続々と話題作を発表する。世界一軽く「街に出かけたくなるスニーカーのような」車いす。 禁煙を促す「たばこを吸いにくい」灰皿。時計をデザインするときは、 宇宙での星や太陽をとらえて時計を認識するという文脈を具現化。 はずしたりかけたりを繰り返しても決してレンズに歪を与えないメガネフレームを創り出した。
さらには、トポロジーという数学理論を応用してデザインした人工心臓や、 超小型の原子炉発電装置、光量子とともに点滴を果たす装置まで研究している。 もちろん、それらはただフォルムをデザインするだけではない。 機能・性能・効能まで徹底的にこだわって、モノづくりのすべての過程にわたって知恵をしぼり、 手を動かしてスケッチをくり返す本来の意味での地道なデザイン実務である。
「音響機器をデザインするなら、エンジニアと同じだけの知識を持たないとできない。 医療機器をデザインするなら、医師と同じだけの知識を持たないとデザインはできないんです」

(左)車いす「CARNA」(1989年) 自分自身が乗りたい車いすを、とデザイン。 明るい色合いや座り心地を追求した座面、徹底した軽量化の工夫が施されている。 ニューヨーク近代美術館(MoMA )永久展示。
(右)クロック「HOLA」(1988年) 中央円盤のくぼみが「時」を表し、分針が円盤に寄り添う。 ラウンド面にあたる光で表情が変化し、天体の動きを意識させる。Gマーク賞受賞。
事実、人工心臓のデザインでは、それを論文にまとめ医学博士号もとっている。並大抵の勉強量ではない。
関わる分野の数だけ知識は増える。医学、数学、工学、物理学、心理学、音響学、 文学や哲学までも吸収し、それらを縦横に論理化、造形化を果たして、新たなデザインの発想に結び付けている。
いのちと向き合う
さらに、これらの学問を統合した先端的なデザイン理論と実技を、 大学教授として若き才能へ伝えている。
「大学の研究室では、『いのちと向き合うデザイン』をテーマとしています。 医療器具などのデザインでドクターやナースの仕事を支えたり、 看護体制の環境をつくることにも取り組んでいます」
いのちと向き合う―。その言葉は、はからずも川崎さん自身の姿勢ともリンクする。
「ものづくりは、命がけだ」と、川崎さんはことあるたびに発言してきた。
膨大な知識を吸収し、モノを使う人にとって、 それがどういう意味をもつモノになるのかを根源までたどり、 まるで命を削るかのように考えに考え抜いてアイデアを生み出す。 己のすべてをかけたデザインだからこそ、企業とも学会とも真剣勝負で渡り合う。
意見が合わなければ、仕事を断ることもしばしばだという。
「徹底してわがままを通します。使う人にとって正しいものであるという確信が持てた提案は、 命がけで守る。ずいぶん損な生き方をしているかもしれませんが」
冒頭で紹介したキーボードのスケッチも、きっとそんな真剣勝負で繰り出したものに違いない。
川崎さんがデザインしたメガネは一昨年の米大統領選副大統領候補として登場した サラ・ペイリン女史がかけていたことで脚光を浴びた。そのことで注目されることには閉口しながらも、 川崎さんは「ああ、これで日本はまだやっていける」と実感したという。

メガネフレーム「Kazuo Kawasaki MP704」。 無駄のない直線的で洗練されたデザイン。 見た目のボリューム感とは対照的に軽く、程よい圧力で頭にフィットする。
「アジア各国で低価格の製品が生産され、あらゆる分野で商品棚を奪われつつあります。 でも、デザインではまだリードできることがいっぱいある。モノづくりのアイデンティティを持ち、 革新を続けていくこと、日本の製造業の未来を創るのは、やはり、モノづくりです」
大阪大からはすでに川崎さんの信念を受け継いだ気鋭のデザインディレクターたちが巣立ち、 企業に新たな活力を与え始めている。
川崎さんの作品は、こう問いかけてくる。
「あなたは、自分のいのち、きもち、そして生き方のかたちに向き合っていますか」

デザインディレクター 医学博士
川崎 和男 (かわさき かずお)
1949年福井市生まれ。
金沢美術工芸大学産業美術科卒業。株式会社東芝に入社後フリーとなり、 デザインディレクターとして伝統工芸品からメガネやコンピュータ、ロボット、 原子力エネルギー、人工臓器、先端医療、宇宙空間の装置化まで幅広く、研究・教育・実務活動を行う。 国内外での受賞歴多数。また、ニューヨーク近代美術館など海外の主要美術館に永久収蔵、永久展示多数。 デザインによる世界平和構築をめざして「Peace-Keeping Design(PKD)」というプロジェクトを提唱している。 大阪大学大学院教授、工学研究科・医学系研究科の教授、 日本産業デザイン振興会グッドデザイン賞審議委員会委員。