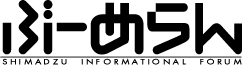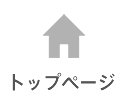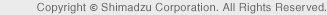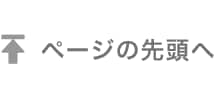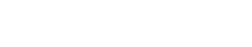 Backnumber
Backnumber

土は言葉でよみがえる

産業活動によって汚染された土壌。その浄化には長い年月と費用がかかる。
それなら、汚染物質がまったくゼロにならなくても、住民を含めた関係者が理解し納得できるような汚染の管理を行い、土地の有効活用法を見つけられないか。知恵と技術を駆使した取り組みが、成果を上げはじめている。
負の遺産
土壌汚染は、根深い環境問題だ。
「水や空気の汚染は、法律により汚染物質の排出を規制すれば、すぐにきれいになります。しかし、土壌はそうはいきません。たとえ汚染物質の排出を規制しても、既に排出された汚染物質は数年、数十年と留まり続け、地下水を汚染し続けるのです」
国際環境ソリューションズ株式会社技術部の佐藤徹朗部長は、問題の難しさをそう指摘する。
同社は「土地・地下水汚染問題解決の専門家集団」として、国内で数多くの土壌浄化実績を有するとともに、有害物質による環境リスク低減、緑地資産などの環境資産活用の評価・コンサルティングサービス、環境に配慮した土地活用まで、幅広いソリューションを提供している。
土壌汚染は経済発展の負の遺産だ。自然由来の土壌汚染もあるが、より大きな問題となるのは、企業の事業活動に伴って発生した有害物質による汚染だ。
明治時代には鉱山の精錬工程で発生する鉱毒による田畑の被害が大きな社会問題となり、近年は工場の生産活動に使用されてきた揮発性有機化合物(VOC)による土壌汚染が顕在化している。VOCの汚染原因は、工場などの作業工程で付着した油などを洗浄するのに用いた溶剤で、微量でも継続して摂取することがあれば、発がんの危険性がある。だが、高度経済成長期には、これらの薬剤が有害である認識がなかったため規制する法律はなく、その場に廃棄されたことも多い。
先に挙げた鉱毒汚染の経験から、農用地を対象とした土壌汚染対策は先行していたが、市街地における土壌汚染は、私有地のために顕在化しにくく、そのまま放置されてきた。その間、汚染物質は、雨水などによって次第に地下へ潜り、地下水脈に混入。1982年に環境省が全国規模で実施した地下水調査で、全体の3割の井戸でVOCが検出されたことで、土壌・地下水汚染の対応が急務と考えられるようになった。それから20年後の2002年に、土壌の特定有害物質の汚染状況を把握し、汚染による人の健康被害を防止することを目的に「土壌汚染対策法」が公布された。
土地に対する執着心
これにより特定の有害物質を製造、使用、処理、保管する施設が規制対象となった。事業を廃止するとき、土地の形質を変更するとき、知事による調査命令時には土壌の調査を行うことが義務付けられた。一方で、住民と良好な関係構築を考える企業のなかには、自主的に土壌や地下水の調査を実施する例もある。
それでも日本における土壌汚染地域の全容はまだ把握されていない。1998年に行われたある調査によれば、土壌汚染調査が望まれる事業所、跡地は、約44万カ所にものぼると推定されている。
汚染が顕在化することも問題だが、より問題となるのは調査の後だ。調査で土壌汚染が確認され、健康被害が生じる恐れがあるとされると、都道府県知事から汚染対策の措置を講ずるよう指示される。指示措置は揚水による拡散防止や不溶化により地下水への流出を遮断する方法が主となるが、実際には、汚染土壌を「掘削除去」してしまう過剰な対策が取られることが多い状況にある。
「日本は土地本位制で、土壌汚染があると『価値が損なわれた土地』との評価を受けてしまうため、汚染は完全に取り除かなければならない(ゼロリスク)という意識が働きます。汚染土壌が掘削除去されることが多いのも、そうした意識が背景にあるからでしょう。確かに掘削してしまえば、短期間でその土地から汚染は消えますが、除去した汚染土が不適切に別のところに廃棄されることもあり、汚染を拡散する危険性も指摘されています。しかも、掘削には莫大な費用やエネルギーもかかります。一方で、土壌・地下水汚染は企業の持つ土地だけの問題ではないため、ゼロリスクを求める近隣住民と、最小限の対策で済ませたい企業との間で確執が起こることも少なくないのです」
土壌・地下水汚染への意識の高まりを契機に、海外の土壌浄化会社が日本で活動を開始したが、リスクの大小とは関係なく、粘土層の土壌についても完全浄化を求める強い声に手を焼き、やがて撤退していった。

世の中的に最適化する
こうした状況を踏まえ、佐藤氏らは汚染状況を「世の中的に最適化する」ことを念頭においたリスクコミュニケーションを重視し、汚染を適切に管理していくためのソリューションを提供している。
「海外では土壌汚染をリスクベースで考えるのが一般的です。汚染された土地をどういった用途で活用をするのか。住宅にするのか、工場にするのか。土地ごとに、その都度、評価基準を決めていこうというもの。汚染された土地の上を商業施設にしている例も多いのです」
佐藤氏はそうした企業と住民との仲立ちをし、双方が納得できる結論に達するまで粘り強く提案と交渉を繰り返す。ときには、行政にも働きかけ、実態に即した規制への変更を促す。時間はかかるが、企業と住民との間のわだかまりも消え、良好な関係を継続していくことができる。
「ただ単に汚染土壌を掘削してきれいにするだけであれば、我々が出ていくことはありません。調査から対策までを、それも汚染されたサイトだけじゃなくて、地域全体で最適化していく。適切に情報を共有して、場所場所で最適な浄化方法を提案して実施する。それが私たちの仕事です」
同社は汚染除去技術でも数多くのカードを持っている。得意とするのは汚染物質を原位置で浄化する技術で、時間がかかりその間の浄化をコントロールする必要はあるが、費用も抑えられ、また汚染土を運び出すこともないため、その土地の建物を壊すことなく事業や活動を継続しつつ浄化できる。
「微生物が多い土壌なら、微生物を活性化して有害物質を分解させる生物処理を、微生物が少ないところでは、酸化剤あるいは還元剤を混合して有害物質を分解する方法をと、その場その場で最適な方法や組み合わせを提案しています」
そこに昨年新たなカードが加わった。島津製作所が開発し、共同で実用化を検証している電気加温法による浄化法だ。土壌に電極を刺して、電流を流すことで、土そのものを電気抵抗体として40~80°Cまで発熱させ、VOCの気化や地下水への脱離、更には微生物による浄化を促すというもの。これまでの手法では、浄化薬剤が浸透しにくく効果が望めなかった粘性土層などでの活躍が期待されている。
「10年近く従来法で浄化を続けていたなかで、粘土層だけにはVOCが残っていたサイトでこの技術の実証試験を行ったところ、わずか1年で目的濃度までVOCを取り除くことができました。粘土層における浄化が問題となっている日本の現状にとって、一つの希望が見えてきたと感じています」
技術と知恵の交わるところに、社会の幸せがある。

国際環境ソリューションズ株式会社 技術部 部長
佐藤徹朗 (さとう てつろう)
1971年生まれ。1997年、北海道大学大学院地球環境科学研究科大気海洋圏環境科学専攻修士課程終了。環境系のコンサルティング会社に勤務した後、2005年、国際航業株式会社に入社。08年事業分割を経て、現在は国際環境ソリューションズ技術部部長。社会人ドクターの取得をめざして、油や揮発性有機化合物(VOC)を分解する微生物の研究にも取り組んでいる。