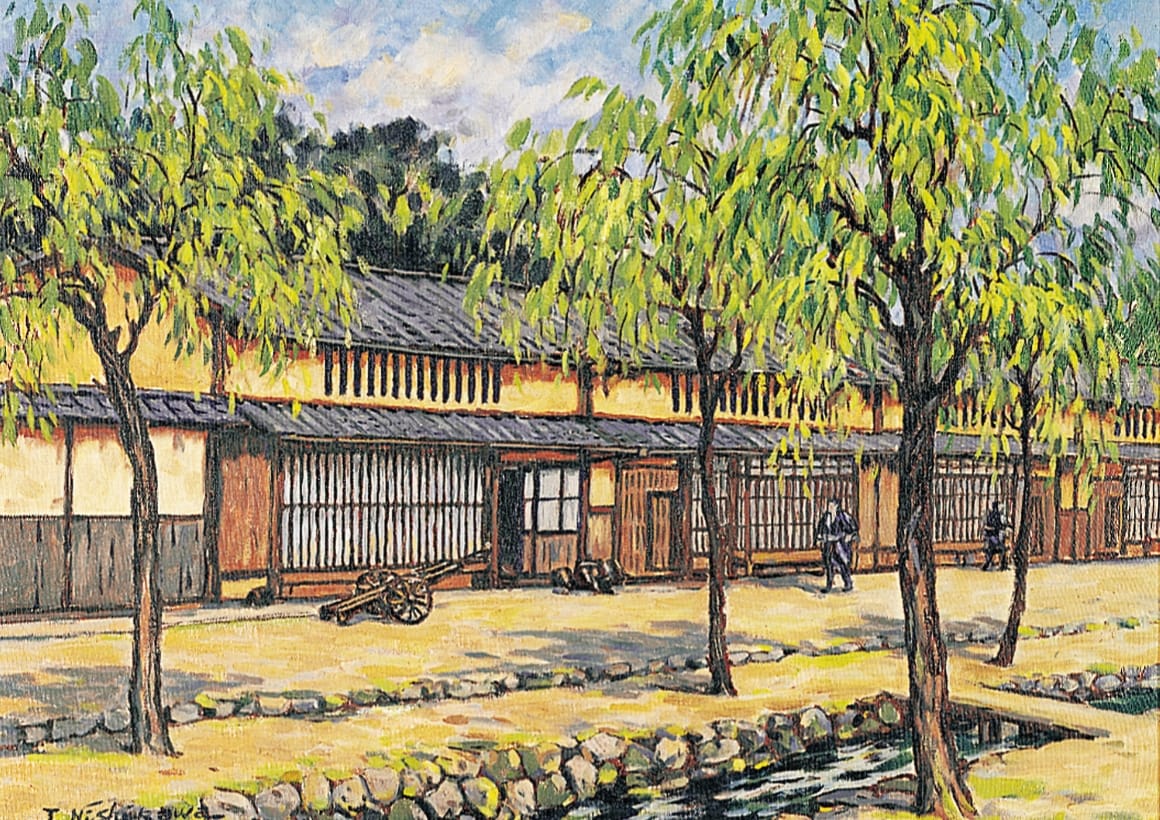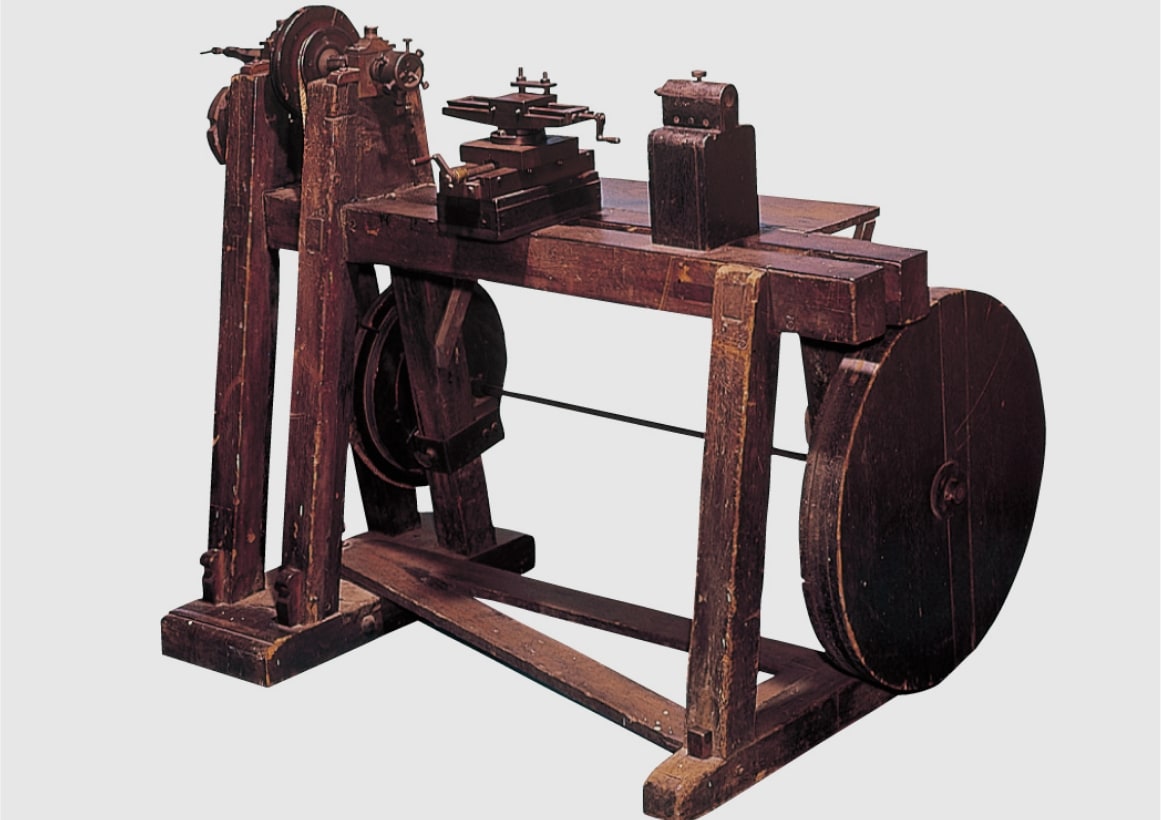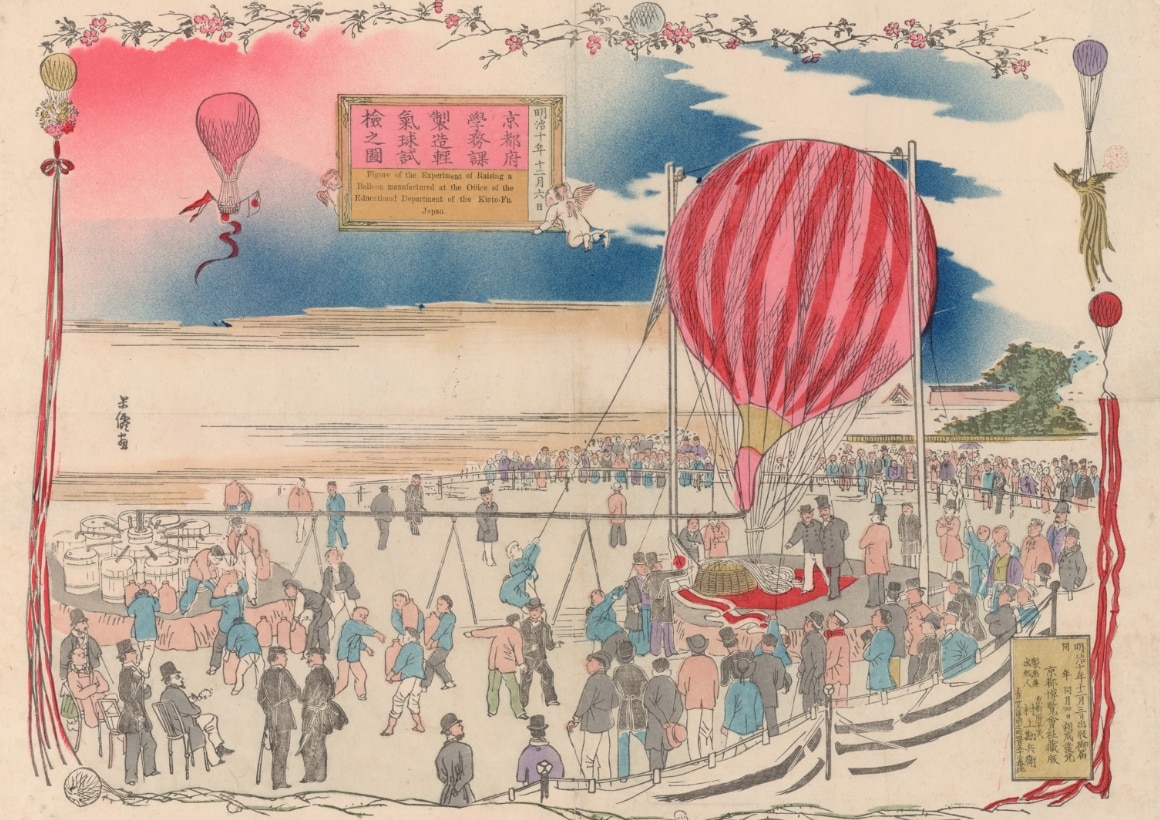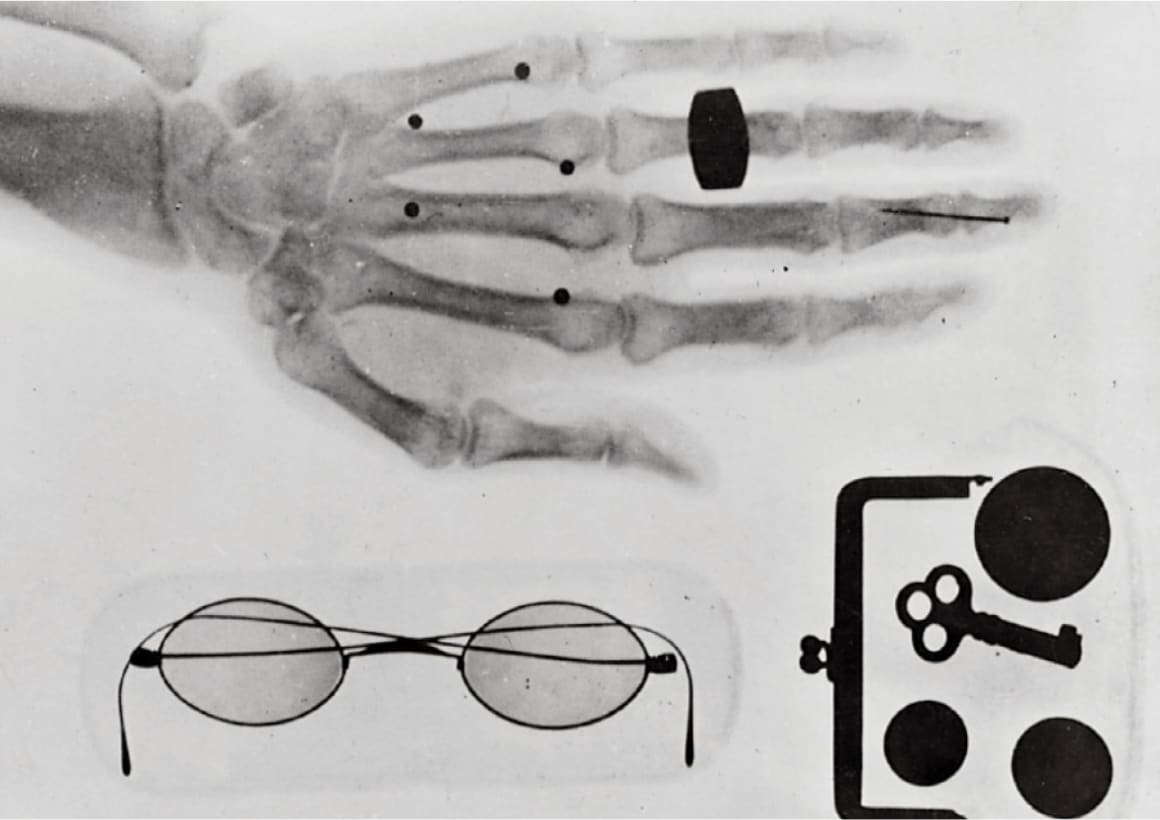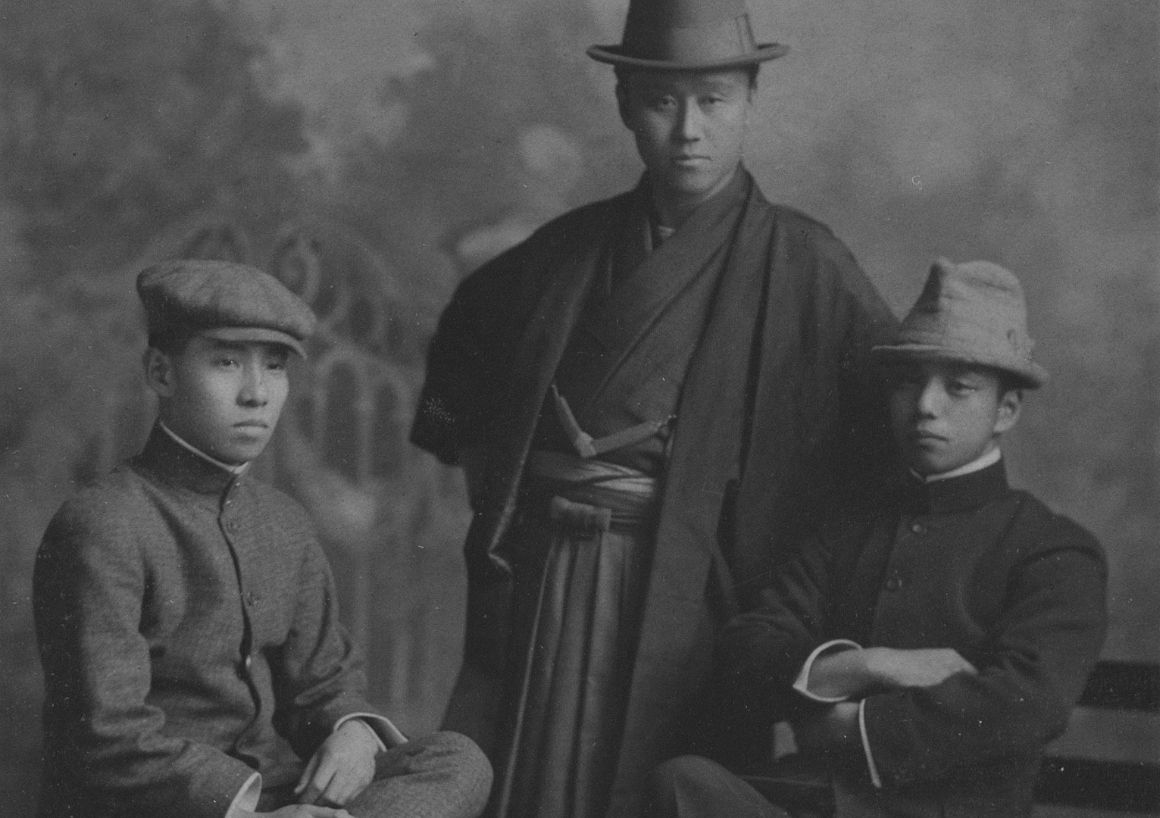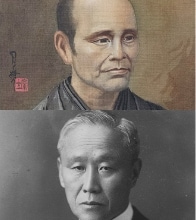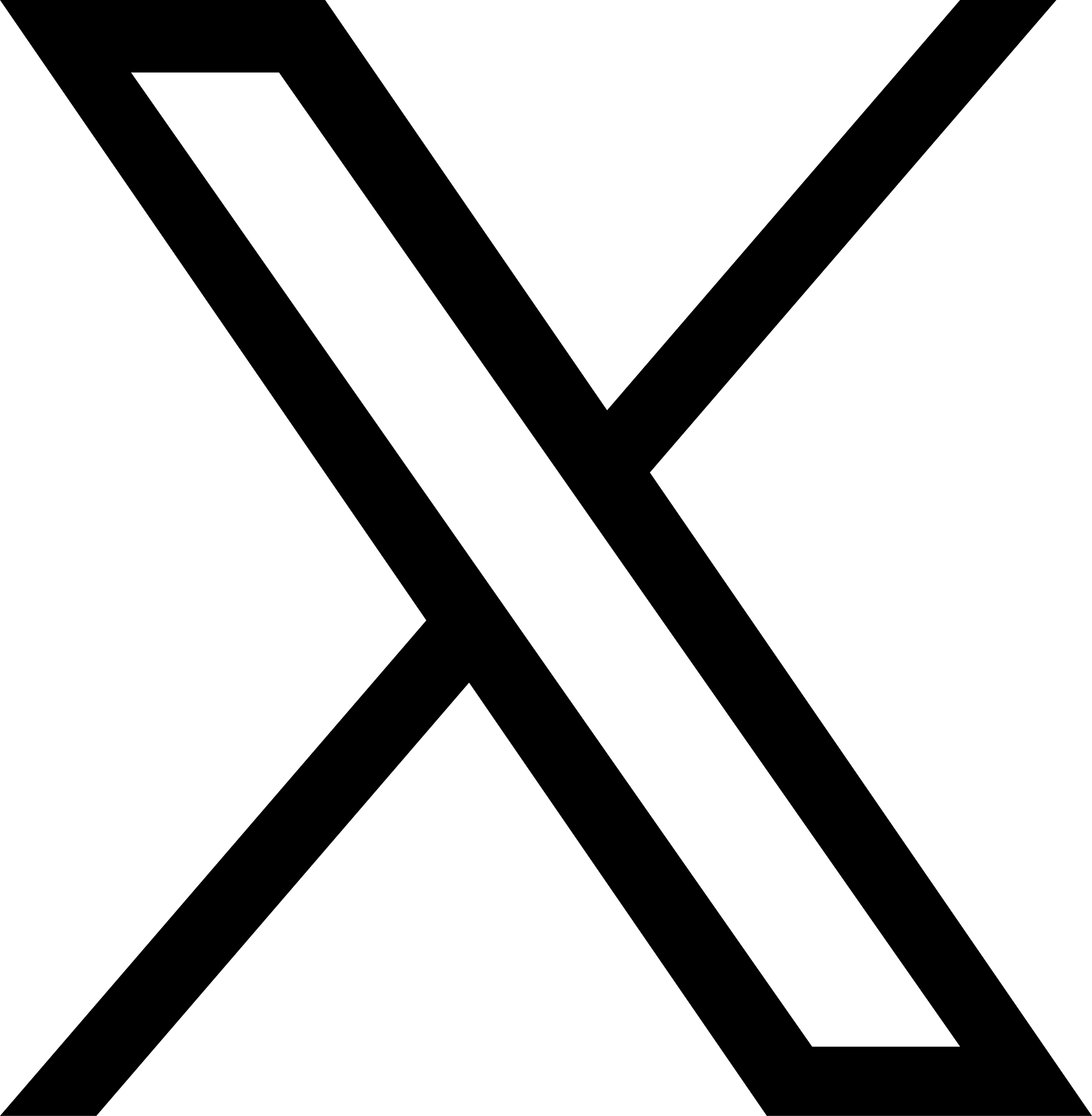島津源蔵のDNA
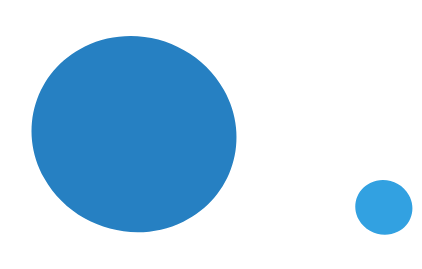
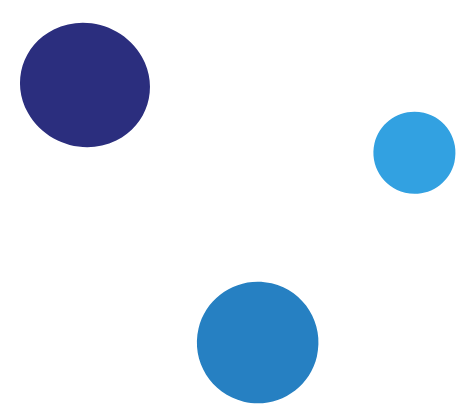
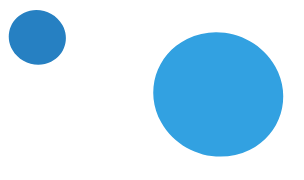
島津源蔵のDNA
源蔵から今に受け継ぐ
挑戦のDNA、その軌跡
技術立国を目指し、
理化学器械の製造事業を興した
初代源蔵。
さらに、その息子3人が事業を拡大。
世の中が求める技術や製品を
生み出すべく挑戦を続け、
現在まで受け継がれている
島津のDNAの軌跡をたどります。
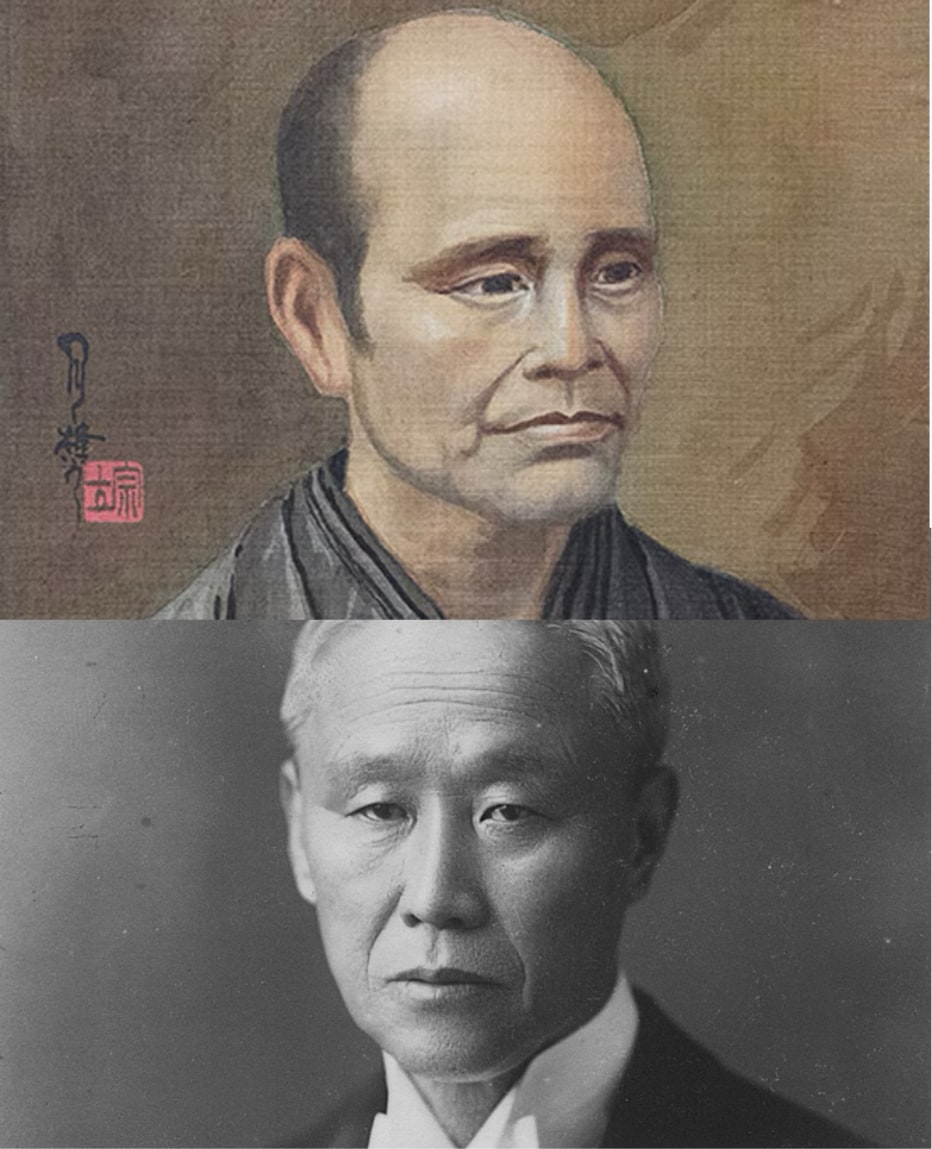


島津家のルーツ
創業者の祖先と薩摩の島津義弘公の縁。300年の時を超えて新たな歴史が紡がれていきます。どのような世の中だったのか、創業の前夜を紹介します。
京都とともに歩み
チャンスをつかんだ初代源蔵
明治維新後の京都で、科学と産業の新たな風を受けた初代源蔵。
近代技術と出会い、外国人技術者から学んだ知識をもとに
島津製作所を創業します。
日本の民間で初の軽気球飛揚、
長男梅治郎も成長
京都御所で軽気球を飛揚させた初代源蔵。その技術力に
多くの人々が驚きました。そして、若くしてその才能を開花させた
長男の梅治郎。父とともにさらなる発展を築きます。
初代源蔵の想いを継いだ
梅治郎が二代源蔵に
初代源蔵の志を受け継ぎ、二代源蔵となった梅治郎。
蓄電池に興味を持ち、X線写真の撮影にも成功します。
科学技術の進展に大きな功績を残していきます。
二代源蔵、
日本の十大発明家の一人に
二代源蔵は、蓄電池の開発を本格化させ、亜酸化鉛の製造に
関する特許を世界各国で取得。その革新性が評価され、
1930(昭和5)年に日本十大発明家の一人に選ばれたのです。
島津を源流とする
いくつもの企業が誕生
蓄電池事業をはじめ島津製作所からいくつもの企業が
誕生しました。その多岐にわたる展開が、技術革新と
挑戦の歴史を物語ります。
二代源蔵を支えた2人の弟
二代源蔵の弟、源吉と常三郎。二人の活躍も事業の発展に
欠かせませんでした。科学技術に情熱を注いだ挑戦のDNAは、
今なお受け継がれています。