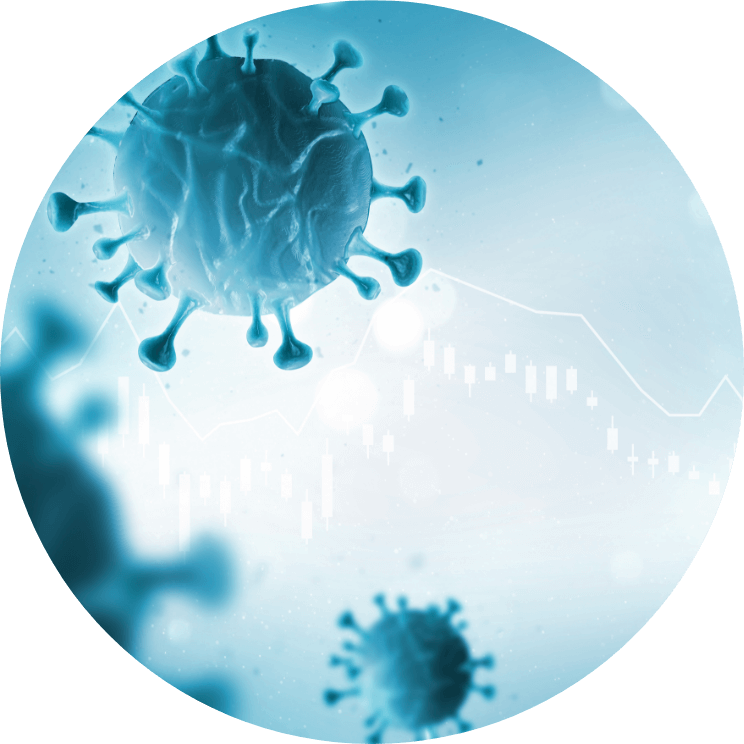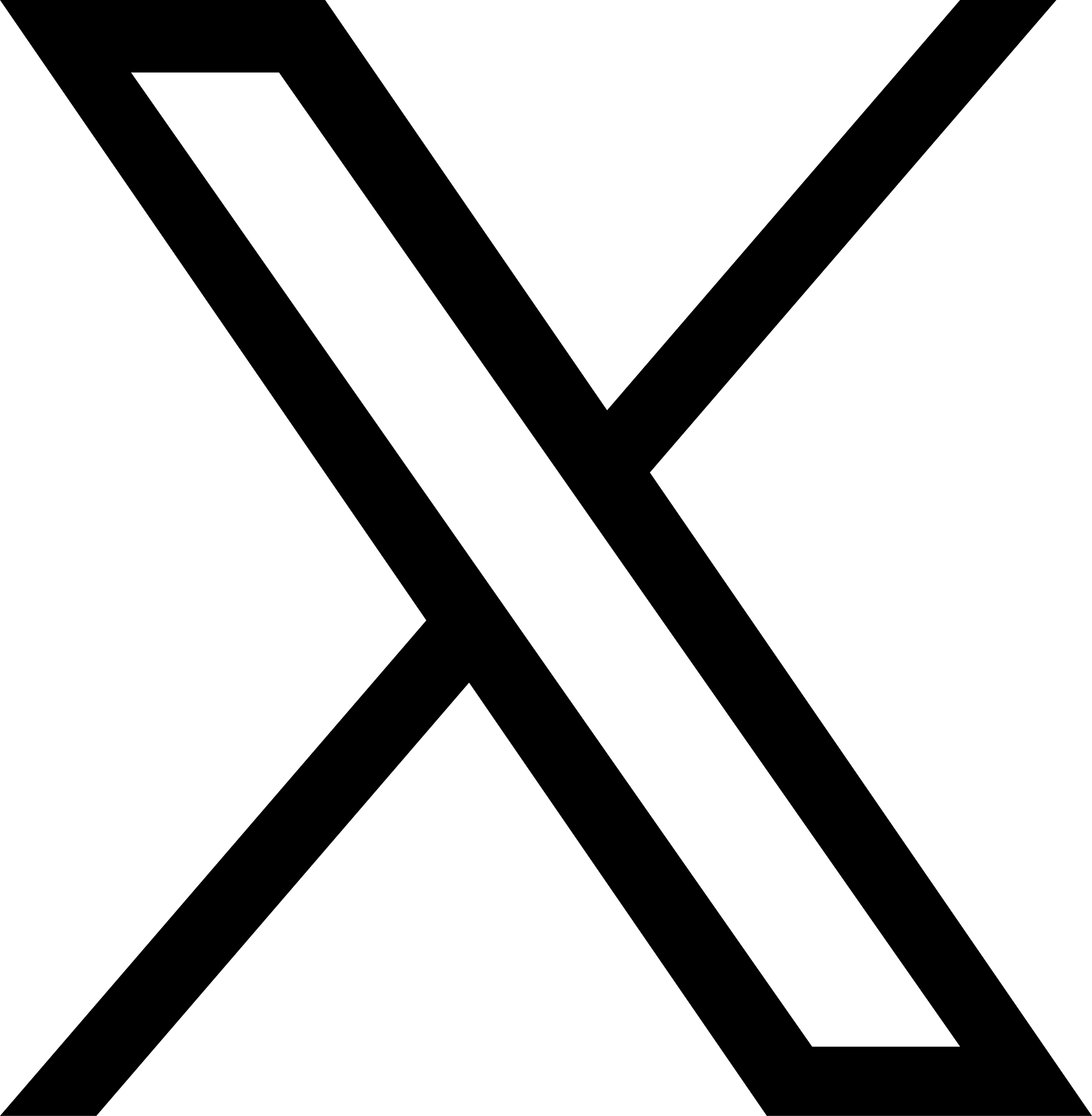社会課題への挑戦
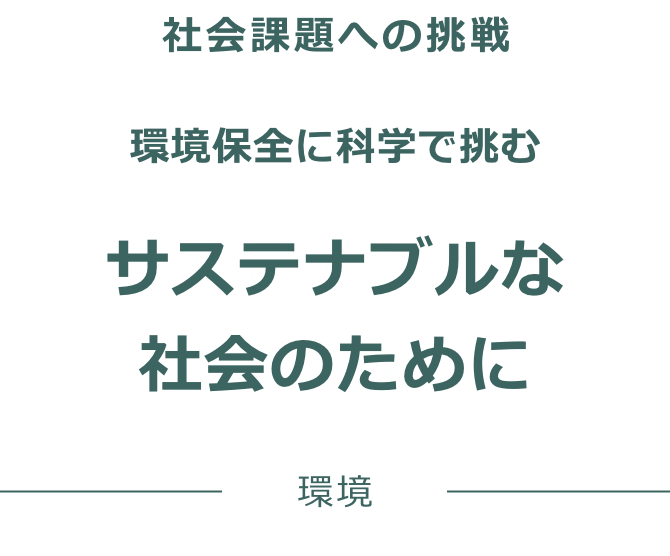
- 近代化のなか、公害・健康被害が深刻化 検査・分析で環境保全に貢献したい
- 機器提供のみならず受託分析事業に拡大 専門会社設立で、環境問題に深く踏み込む
- “人と地球の健康”への願いを実現する グループ一丸となって目指す環境と調和した社会づくり
近代化のなか、公害・健康被害が深刻化
検査・分析で環境保全に貢献したい
産業がもたらした公害との闘い
日本では、1950年代後半から1970年代にかけて著しい経済成長を遂げましたが、一方で大気や水質の汚染など、深刻な公害を引き起こしました。亜硫酸ガスによる「四日市ぜんそく」、有機水銀による「水俣病」、窒素酸化物による光化学スモッグの発生などが次々に大きな社会問題となりました。
政府は、1967(昭和42)年に公害対策基本法、翌年には大気汚染防止法、1971(昭和46)年に水質汚濁防止法など次々に法整備を進めました。島津製作所も、自社技術でできることは何かを繰り返し議論し、分析計測機器で汚染物質の発生原因を科学的に究明すること、汚染物質の無人連続測定により監視できる機器を供給することなどを決め、1971(昭和46)年6月に環境機器部を立ち上げました。政府も翌7月に環境庁を発足させました。
汚染物質を「24時間365日」常時測定する分野に参入
分析計測機器は、対象となる試料を研究室などに持ち込み、そこに設置した機器で測定を行います。一方、環境問題においては、測定対象物が工場から排出されるガスや水などであり、各現場で連続的に常時測定できる機器が必要でした。例えば、火力発電所が排出するガスの測定を行う場合、該当施設の発電プロセスを理解して、各現場に最適な前処理機器を内蔵した自動分析機器を設置しなければなりません。屋内外を問わず設置でき、風雨や周囲の温度変動などにも影響されず、発電所が稼働している24時間365日、休止することなく測定し続ける必要がありました。
島津は、長年培った分析測定の基礎技術を生かしながら、これらのニーズに応えました。現在も24時間365日の連続測定は社会の至るところで行われています。
環境庁が発足した当時、世界初の光化学スモッグ測定実験車が導入されたことが話題になりました。島津が製作を担当したこの実験車は、大気を取り込んで光化学スモッグ発生のメカニズムを明らかにしたいとの要望に基づいたもので、その後、日本自動車研究所にも納入しました。
水質汚濁の測定を画期的手法で変革
大気だけでなく水質保全にも、島津は貢献しています。1964(昭和39)年、新潟県阿賀野川流域で起こった有機水銀中毒に対し、その検出に島津のガスクロマトグラフが使用されました。また分光光度計も使用されました。工場排水などによる水質汚濁が大きな社会問題となり、排水に関する規制も定められていきました。企業や工場の排水管理が急務となるなか、当時の水質汚濁モニタリングにはいくつかの指標が使われるようになりましたが、薬剤を多く要したり、測定誤差や測定時間などの課題がありました。
島津は、水の中に存在する有機物を構成する炭素の量から、水の汚れを示す指標のTOC(全有機体炭素)の量に着目して製品開発に注力しました。その有効性や合理性を規制当局に示し、1972(昭和47)年には水質汚濁防止法で定められた公共用水域の水質汚濁を常時監視するためのTOC連続自動計測機および実験室用TOC計を発売。多くの事業所で導入され、水質保全に貢献しました。これら製品は、その後もリニューアルを継続して性能を向上させ、現在も産業排水の監視、河川や湖、海、地下水、そして水道水の水質基準を支えるだけでなく、医薬品や半導体の製造管理と評価、カーボンニュートラル等の研究用途など幅広い分野で使用されています。

機器提供のみならず受託分析事業に拡大
専門会社設立で、環境問題に深く踏み込む
受託分析で環境に係る科学的知見を提供
環境汚染への対応は深刻かつ急務で、官公庁や企業などから島津のもとに分析や調査、評価を依頼したいという声が寄せられました。社内に設置した分析センターや研究開発部門でその対応をしていましたが、各方面からの依頼を請け負う専門会社を設立することを決めました。1972(昭和47)年4月、受託分析事業を行う(株)京都科学研究所、現在の(株)島津テクノリサーチ(以下、STR)です。
ダイオキシンの脅威に島津はいち早く取り組む
1977(昭和52)年のオランダでの調査報告以来、ごみ焼却施設におけるダイオキシンの問題は欧米諸国で注目され、研究と対策が進められました。ダイオキシンとは廃棄物を焼却した際などに発生する物質で、強い毒性を有します。環境中に拡散されたダイオキシンは土壌や湖沼などに堆積(たいせき)し、農産物や魚介類を通じて人に健康被害をもたらします。
日本で各地のゴミ焼却施設の緊急調査を行った際、民間として最初に分析したのが、いち早くこの問題に着目していたSTRでした。1995(平成7)年には、野菜の高濃度汚染が報道され、日本全国での対策が急務となりました。STRは、すでに大学や企業などと連携しながらダイオキシン分析の技術や有用性の高いデータの蓄積、分析業務の一貫体制を築いていたことから、その先駆者として法整備やガイドライン作成に高度分析技術データを提供することでサポートし、各種分析マニュアルやJISの整備にも力を発揮したのです。
こうしてダイオキシンの削減対策や処理技術の改良が飛躍的に進み、2000(平成12)年前後には、従来の国内排出量の95%以上の削減に成功したのです。
未来の子どもの健康と環境作りをサポートするSTR
STRの技術や知見はその後も発展し、人や生物への毒性が高い物質である残留性有機汚染物質(POPs)の対策など、確かな歩みを進めています。2011(平成23)年からは、環境省の国家プロジェクトにも参画しています。化学物質など環境中の有害物が子どもの成長・発達に悪影響を及ぼす可能性が指摘されたことにより、10万組の親子に大規模な疫学調査「エコチル調査」を行うことになったのです。STRは、収集された膨大な母乳や血液、尿試料をはじめ、生活環境に関わるさまざまな研究テーマにおける化学物質の分析を担っています。この事業では同時に島津製の最新の分析機器GC-MS/MSやLC-MS/MSも貢献しています。

“人と地球の健康”への願いを実現する
グループ一丸となって目指す環境と調和した社会づくり
島津製作所は、社是「科学技術で社会に貢献する」に加え、1992(平成4)年に「『人と地球の健康』への願いを実現する」という経営理念を制定しました。1996(平成8)年には国連大学「環境監視プロジェクト」への支援を始め、18年にわたりアジア地域を中心に環境モニタリングを実施するとともに、参加研究機関の分析技術の向上と人的ネットワークの強化を図りました。
環境マネジメントシステムISO14001認証については、1997(平成9)年に本社・三条工場で取得し、2015(平成27)年には全ての生産・研究開発・営業拠点と主要な関係会社で統合認証を取得、事業活動における環境への取り組みをグループ全体で行っています。
社員への啓発のために、1999(平成11)年には環境教育活動チームを発足させ、2001(平成13)年からは社外活動として環境出前講座を実施してきました。当社と学生が生物多様性を題材にしたオリジナルのカードゲームを共同制作し、それを活用するほか、モノを大切にすることを伝える「ごみとリサイクル」の授業などを、京都市内の小学校を中心にのべ1万人以上の子どもたちに実施しています。

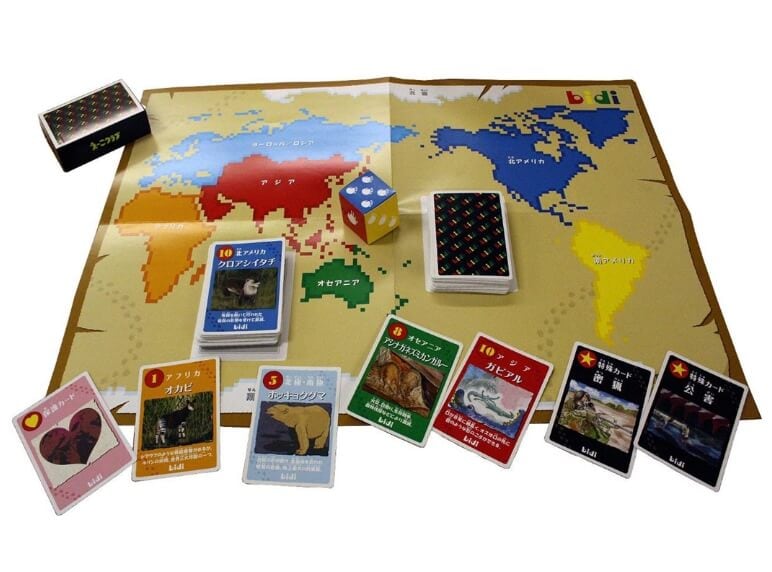
カードゲーム
持続可能な社会に向けて
2002(平成14)年から製品のエコ化に取り組み、2010(平成22)年に地球環境の負荷低減を目指した製品とサービスをお客様に提供する活動として本格化させました。省エネなど従来製品に比べて特に優れた環境性能を実現した新製品に対して「エコプロダクツPlus」を認定する自社制度を設けたものです。認定製品への更新により、削減可能となるCO2排出量やランニングコストを試算するエコシミュレーションソフトを用意するなど、お客様への情報提供も行っています。2019(令和元)年からは、すべての新製品について従来よりも環境負荷を少なくするための規定を設けています。
地球レベルの課題である気候変動、エネルギー問題に積極的に取り組むため、2021(令和3)年に「RE100」などの国際イニシアティブに加盟しました。2050年までに事業活動で使う電力をすべて再生可能エネルギー起因とすることを約束し、日本国内の工場や研究所など主要拠点で使用する電力を再生可能エネルギー100%由来のものに切り替えました。世界に広がる島津の拠点においても持続可能な社会への実現に向けて環境経営の歩みを進めています。
社会課題への挑戦